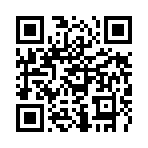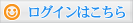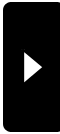昭和東南海地震と戸籍
2012年08月31日
先日、東海、東南海、南海地震などが同時発生するマグニチュード9クラスの「南海トラフ巨大地震」について、国の二つの有識者会議が、被害想定を発表していましたが、死者数は最大で32万3000人で、そのうち津波による死者は全体の7割の23万人に達するとのことでした。
なんとも怖ろしい数字です。
ところで、先日、相続手続きのために三重県熊野市に請求していた除籍謄本が今日、届いて、中身を確認していたところ、「昭和19年12月7日津浪ニ罹リ滅失ニ付昭和21年6月1日本戸籍再製ス」という記載がありました。
「昭和19年12月7日」で検索すると、確かに「マグニチュードは 7.9、地震発生の10分後には津波も発生し、熊野灘沿岸では 6~8mに達した。」とのことのようです。
たくさん、戸籍を見てきましたが、今回、津波による滅失再製の記載のあるものを初めて見ました。
このときの震災は、敗色も濃厚となった太平洋戦争末期の惨事だったため、国民の戦意喪失を恐れた軍部によって被害状況は長い間隠されていたようです。
それでか、再製が終戦の翌年になっています。過去の津波の証拠となる除籍謄本ですね。
なんとも怖ろしい数字です。
ところで、先日、相続手続きのために三重県熊野市に請求していた除籍謄本が今日、届いて、中身を確認していたところ、「昭和19年12月7日津浪ニ罹リ滅失ニ付昭和21年6月1日本戸籍再製ス」という記載がありました。
「昭和19年12月7日」で検索すると、確かに「マグニチュードは 7.9、地震発生の10分後には津波も発生し、熊野灘沿岸では 6~8mに達した。」とのことのようです。
たくさん、戸籍を見てきましたが、今回、津波による滅失再製の記載のあるものを初めて見ました。
このときの震災は、敗色も濃厚となった太平洋戦争末期の惨事だったため、国民の戦意喪失を恐れた軍部によって被害状況は長い間隠されていたようです。
それでか、再製が終戦の翌年になっています。過去の津波の証拠となる除籍謄本ですね。
何事も全体最適を目指す
2012年08月28日
有難いことに、ご相談は、毎日、毎日、あります。私のような職業の場合は、何事も、ご相談から仕事が始まります。 ご相談内容は、会社や個人の将来に関わる大切な問題が多いですから、当然、大切に扱います。
ご相談の一つ一つを、けっして、ぞんざいに扱うようなことはありません。
ですが、中には困ったご相談もあります。違法行為や倫理に反するご相談はもちろんですが、それ以外に困るのが、全体のある部分だけのご相談というものです。
もちろん、それもご相談ですから、ぞんざいに扱うことはないわけですが、法律や企業経営に関する問題は、全体として組み物のようになっていることが多いと思います。
そのある部分の問題についてだけ、正解と思う答えをさせていただくとしても、他の事柄との兼ね合いで、その部分回答が、全体としては不適切なものになっていることもあるわけです。
であるにも関わらず、部分のみの回答を、せっかちに求められても、返答に窮する、あるいは、返答することによる悪影響を考えてしまうと、どうしても回答がし難くなります。
これは、何ももったいをつけているわけでも、ご相談をぞんざいに扱っているわけでもないのです。ですので、そのあたりをご説明申し上げて、ご理解を得る必要があるわけですね。
とにかく、ご相談に対する回答は、将来に禍根を残さないために全体最適を旨といたしております。
ご相談の一つ一つを、けっして、ぞんざいに扱うようなことはありません。
ですが、中には困ったご相談もあります。違法行為や倫理に反するご相談はもちろんですが、それ以外に困るのが、全体のある部分だけのご相談というものです。
もちろん、それもご相談ですから、ぞんざいに扱うことはないわけですが、法律や企業経営に関する問題は、全体として組み物のようになっていることが多いと思います。
そのある部分の問題についてだけ、正解と思う答えをさせていただくとしても、他の事柄との兼ね合いで、その部分回答が、全体としては不適切なものになっていることもあるわけです。
であるにも関わらず、部分のみの回答を、せっかちに求められても、返答に窮する、あるいは、返答することによる悪影響を考えてしまうと、どうしても回答がし難くなります。
これは、何ももったいをつけているわけでも、ご相談をぞんざいに扱っているわけでもないのです。ですので、そのあたりをご説明申し上げて、ご理解を得る必要があるわけですね。
とにかく、ご相談に対する回答は、将来に禍根を残さないために全体最適を旨といたしております。

経営者は孤独?
2012年08月27日
今、経営者さんや次期経営者さんから、さまざま、ご相談を受ける中で、「経営者は孤独か?」ということについて改めて考えてみました。
ちなみに、「経営者 孤独」で、ググると、出てきますね、たくさんのサイトが。
で、どういうふうに孤独なのかと見てみれば、概ね、そこに書かれているのは、下記のようなことのようです。
会社の経営者と対比する会社の従業員さんは、〝すること〟に制約があります。それは、会社の指揮命令のもとに働く立場ですから当然ですよね。
でも、経営者には、そういう制約がありません。もちろん、資金、設備、人材、ノウハウなどの経営資源の有無によって、経営に制約があることは、もちろんですが、そうした持てる資源の範囲の中で、〝何をするか〟は経営者だけが決めることであり、その結果責任は基本的に全て経営者が負うことになります。
ですから、一緒に働く仲間ではありますが従業員とは違う立場で経営者は悩み、孤独感を持つということ。
では、この孤独感を解消するためには、どうすれば良いのでしょうか?
この問いに対する答えは、実際の経営者さんによって、いろいろなお答えがあるでしょうし、現実に何らかの克服方法をお持ちだと思います。中には、それは宿命と諦めて違う場所で孤独感を紛らわすという方もあるかもしれませんね。
ですので、どれが正解というのはないのかもしれませんが、先達のご意見に沿って、あえて、一つ挙げさせていただくとするならば、それは、経営者自身が自信を持つために勉強することであり、その勉強に基づく経営方針(経営戦略と言っても良いと思います。)を確立することではないかと思います。
あれをやってみようか?これをやってみようか?・・・制約のない分、なんらかの方針、戦略がないと常に悩みの宇宙の中に身を置くことになり、不安がついて回ります。
先日の事業承継のお話の中でも社長が、「景気の良いときはブームや流れに身を任せておけば良いので経営なんて誰でも出来る。でも、景気の波に左右されることなく長く商売を続けて行くことは簡単じゃない。」と、仰いました。
ブームや流れに関係なく長く商売を続けて行かれる経営者は、やはり、それなりの経営戦略をお持ちです。
また、別の会社の社長には、「経営者がモラルのある経営戦略を作り、それに基づいた戦術を従業員さんに授けて、そのとおりに会社を運営することができれば、経営者と従業員の間には相互に信頼関係が生まれ、会社は良い方向に向かうはずです。そのとき、経営者の孤独感はかなり小さくなる。」と、教えて貰ったことがあります。
「経営者は孤独」ということについて、どう、思われますか?
ちなみに、「経営者 孤独」で、ググると、出てきますね、たくさんのサイトが。
で、どういうふうに孤独なのかと見てみれば、概ね、そこに書かれているのは、下記のようなことのようです。
会社の経営者と対比する会社の従業員さんは、〝すること〟に制約があります。それは、会社の指揮命令のもとに働く立場ですから当然ですよね。
でも、経営者には、そういう制約がありません。もちろん、資金、設備、人材、ノウハウなどの経営資源の有無によって、経営に制約があることは、もちろんですが、そうした持てる資源の範囲の中で、〝何をするか〟は経営者だけが決めることであり、その結果責任は基本的に全て経営者が負うことになります。
ですから、一緒に働く仲間ではありますが従業員とは違う立場で経営者は悩み、孤独感を持つということ。
では、この孤独感を解消するためには、どうすれば良いのでしょうか?
この問いに対する答えは、実際の経営者さんによって、いろいろなお答えがあるでしょうし、現実に何らかの克服方法をお持ちだと思います。中には、それは宿命と諦めて違う場所で孤独感を紛らわすという方もあるかもしれませんね。
ですので、どれが正解というのはないのかもしれませんが、先達のご意見に沿って、あえて、一つ挙げさせていただくとするならば、それは、経営者自身が自信を持つために勉強することであり、その勉強に基づく経営方針(経営戦略と言っても良いと思います。)を確立することではないかと思います。
あれをやってみようか?これをやってみようか?・・・制約のない分、なんらかの方針、戦略がないと常に悩みの宇宙の中に身を置くことになり、不安がついて回ります。
先日の事業承継のお話の中でも社長が、「景気の良いときはブームや流れに身を任せておけば良いので経営なんて誰でも出来る。でも、景気の波に左右されることなく長く商売を続けて行くことは簡単じゃない。」と、仰いました。
ブームや流れに関係なく長く商売を続けて行かれる経営者は、やはり、それなりの経営戦略をお持ちです。
また、別の会社の社長には、「経営者がモラルのある経営戦略を作り、それに基づいた戦術を従業員さんに授けて、そのとおりに会社を運営することができれば、経営者と従業員の間には相互に信頼関係が生まれ、会社は良い方向に向かうはずです。そのとき、経営者の孤独感はかなり小さくなる。」と、教えて貰ったことがあります。
「経営者は孤独」ということについて、どう、思われますか?
今日も事業承継のお話に
2012年08月24日
今日は午後から建設業許可の更新手続きの終わったS工務店さんに許可通知書をお届けに行きましたところ、社長さんから暫し事業承継についての思いを中心にお話をお聞きしました。
大工の見習い時期を含めて約40年間、建築に携われてきた社長さんですが、昨今、ふっと仕事と離れて気楽に成りたいと思うことがあるとのこと。でも、この会社には後継予定者の息子さんがありますので、今、商売をやめるわけにはゆきません。
さて、事業承継のお話では、「後継者は先代と違ってもいいから、これなら他人に負けないという独自の能力がないと、いけないと思う。」ということでした。
とりあえず事業を承継したとしても、仕事の勘所を押さえる能力は先代の独自のもの、会社の長年の信用も先代のもの。そうなると後継者は会社を受け継いだとしても、自身の能力や信用は自前で作って行く必要があるという意味だと私なりに理解しました。
小規模な会社では、仕事の処理能力や信用は社長の属人的なものということですね。つまり、その会社の独自資源が社長の独自資源とイコールなわけです。
確かに改めて、そう言われてみればそうですね。だから、小規模会社の事業承継は難しいと仰りたかったわけですね。S工務店さんの社長さんは、そう言いながら、後継者が我が子ゆえの心配があるというふうでした。
競争市場の中で独自資源を持ち、それをもとに差別化ポイントを作る必要がある。そこで、受け継いだものもあるとはいえ、二代目社長には試練が待っているということですね。
事業承継と言えば、おうおうにして株式、相続、税金、債務などの問題に偏った議論のなされかたが多いですが、今日は、経営戦略の面でも、もっと、事業承継を研究しないといけないなと思いました。
大工の見習い時期を含めて約40年間、建築に携われてきた社長さんですが、昨今、ふっと仕事と離れて気楽に成りたいと思うことがあるとのこと。でも、この会社には後継予定者の息子さんがありますので、今、商売をやめるわけにはゆきません。
さて、事業承継のお話では、「後継者は先代と違ってもいいから、これなら他人に負けないという独自の能力がないと、いけないと思う。」ということでした。
とりあえず事業を承継したとしても、仕事の勘所を押さえる能力は先代の独自のもの、会社の長年の信用も先代のもの。そうなると後継者は会社を受け継いだとしても、自身の能力や信用は自前で作って行く必要があるという意味だと私なりに理解しました。
小規模な会社では、仕事の処理能力や信用は社長の属人的なものということですね。つまり、その会社の独自資源が社長の独自資源とイコールなわけです。
確かに改めて、そう言われてみればそうですね。だから、小規模会社の事業承継は難しいと仰りたかったわけですね。S工務店さんの社長さんは、そう言いながら、後継者が我が子ゆえの心配があるというふうでした。
競争市場の中で独自資源を持ち、それをもとに差別化ポイントを作る必要がある。そこで、受け継いだものもあるとはいえ、二代目社長には試練が待っているということですね。
事業承継と言えば、おうおうにして株式、相続、税金、債務などの問題に偏った議論のなされかたが多いですが、今日は、経営戦略の面でも、もっと、事業承継を研究しないといけないなと思いました。
タグ :事業承継
自社の差別化ポイントと顧客の価値基準
2012年08月22日
先日の事業承継のご相談の中で、私は自社の差別化ポイントに合った顧客の維持、開拓に力を入れましょうとお話ししました。
自社の差別化ポイントは顧客に選んでいただく際の決定打ですから、当然、自社の差別化ポイントと顧客の価値基準が合っていないとビジネスとして成立しません。
自社の差別化ポイントに合った顧客というのは、自社の差別化ポイントを商品やサービスの選択基準とする顧客です。顧客の選択基準に合った商品やサービスを提供し続けることができれば、その企業は顧客に選ばれ続けることになります。
これは、当然と言えば当然なのですが、経営戦略上の整理ができていないと、意外に落とし穴に嵌っている場合があります。
では、自社の差別化ポイントに合わない顧客を追いかけるとどうなるか?
当然、ロスばっかりで実が上がらないという結果に終わりますよね。
ですから、だれかれなしに顧客として追うのではなく、しっかり分類(セグメンテーション)して、自社の差別化ポイントを正当に評価してもらえる顧客に対して営業活動を集中して行いましょうということです。
でも、分類して集中して営業活動を行うことは営業対象を絞ることに他なりませんから、間違った分類の仕方をすると、単に市場を狭めるだけになり、不本意な結果に終わる確率が高まります。
従って、顧客を分類する場合は、しっかりとした経営戦略を練り、これに基づき徹底的に考え抜くことが大切ですと申し上げました。
自社の差別化ポイントは顧客に選んでいただく際の決定打ですから、当然、自社の差別化ポイントと顧客の価値基準が合っていないとビジネスとして成立しません。
自社の差別化ポイントに合った顧客というのは、自社の差別化ポイントを商品やサービスの選択基準とする顧客です。顧客の選択基準に合った商品やサービスを提供し続けることができれば、その企業は顧客に選ばれ続けることになります。
これは、当然と言えば当然なのですが、経営戦略上の整理ができていないと、意外に落とし穴に嵌っている場合があります。
では、自社の差別化ポイントに合わない顧客を追いかけるとどうなるか?
当然、ロスばっかりで実が上がらないという結果に終わりますよね。
ですから、だれかれなしに顧客として追うのではなく、しっかり分類(セグメンテーション)して、自社の差別化ポイントを正当に評価してもらえる顧客に対して営業活動を集中して行いましょうということです。
でも、分類して集中して営業活動を行うことは営業対象を絞ることに他なりませんから、間違った分類の仕方をすると、単に市場を狭めるだけになり、不本意な結果に終わる確率が高まります。
従って、顧客を分類する場合は、しっかりとした経営戦略を練り、これに基づき徹底的に考え抜くことが大切ですと申し上げました。
タグ :経営戦略