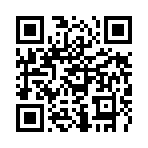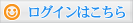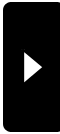専門書のDM
2010年01月29日
行政書士の事務所には、業務の手引になる専門書のDMが頻繁にやってきます。たまに買いたいと思う本の案内もありますが、書店で買うことのほうが多いです。なぜなら、この手の専門書の中には、きょうび、インターネットで集められる通達や書式などの寄せ集め的なものも結構あるからです。
ある程度、独自の解説を加えた良書もあるにはありますが、それでも、分厚い本の半分くらいが法令通達集だったりするのもあるのです。それでいて、専門書だけに売れる数の少なさからでしょうが、高い!たいてい3000円~6000円くらいします。DMだけで飛び付いて、がっかりするのは嫌ですからね。 法令の改廃が頻繁に行われるので、すぐに時代遅れになってしまうのも、この手の本の特徴です。買った直ぐあとに改定版が出ることも多いのです。
法令の改廃が頻繁に行われるので、すぐに時代遅れになってしまうのも、この手の本の特徴です。買った直ぐあとに改定版が出ることも多いのです。
また、この手の本に多い特徴として○○○○研究会などという覆面レスラーが著者のような誰が書いたか解らない本がけっこうあるというのがあります。それでいて権威があったりして、役所の窓口担当者も読んで、その本に沿った法令の運用がなされたりしている現実があります。不思議な専門書です。おそらく役所の関係者が書いていると思うのですが、以前、官僚の人が名前を貸してアルバイトをしていると問題になったことがあった記憶があります。そいうこともあって、覆面著者になっているのかもしれません。
でも、いまだに本名を出している本もあります。会社法の改正時の法務省の担当者の本などがそれにあたります。これなど、改正担当者ですから、当然、権威があり実際の解釈運用に影響を与えるのは必至です。本来、役所が解釈運用を示して国民に示すの筋だと思います、もちろんタダで。それが、高い本を買って勉強せーというのは、いかにもおかしいと思うですが、いかがでしょう。
ある程度、独自の解説を加えた良書もあるにはありますが、それでも、分厚い本の半分くらいが法令通達集だったりするのもあるのです。それでいて、専門書だけに売れる数の少なさからでしょうが、高い!たいてい3000円~6000円くらいします。DMだけで飛び付いて、がっかりするのは嫌ですからね。
 法令の改廃が頻繁に行われるので、すぐに時代遅れになってしまうのも、この手の本の特徴です。買った直ぐあとに改定版が出ることも多いのです。
法令の改廃が頻繁に行われるので、すぐに時代遅れになってしまうのも、この手の本の特徴です。買った直ぐあとに改定版が出ることも多いのです。また、この手の本に多い特徴として○○○○研究会などという覆面レスラーが著者のような誰が書いたか解らない本がけっこうあるというのがあります。それでいて権威があったりして、役所の窓口担当者も読んで、その本に沿った法令の運用がなされたりしている現実があります。不思議な専門書です。おそらく役所の関係者が書いていると思うのですが、以前、官僚の人が名前を貸してアルバイトをしていると問題になったことがあった記憶があります。そいうこともあって、覆面著者になっているのかもしれません。
でも、いまだに本名を出している本もあります。会社法の改正時の法務省の担当者の本などがそれにあたります。これなど、改正担当者ですから、当然、権威があり実際の解釈運用に影響を与えるのは必至です。本来、役所が解釈運用を示して国民に示すの筋だと思います、もちろんタダで。それが、高い本を買って勉強せーというのは、いかにもおかしいと思うですが、いかがでしょう。
相続手続き
2010年01月28日
相続手続きでポピュラーなのは不動産の相続手続きですが、今回は預貯金や簡易保険の相続手続きです。簡単にできそうな手続きですが、仕事の忙しい一般の方には、なかなか大変です。相続人は6人。うち一名は未成年者で相続人のうちの一人の実子です。つまり、その未成年者は相続人の実子であり被相続人の孫で養子なのです。
このことを一般の方が口で説明するのは大変です。しかも相手は銀行が2行、農協と郵便局。それぞれ、行くたびに「あれとこれを揃えてください。」と言われるのですが、それぞれに微妙に違っていて混乱するばかり。そこで、私、行政書士へのご依頼です。
新年、明けまして間もなく一ヶ月ですが、来月の第一週で私の事務所の業務もそろそろ落ち着きそうかなという感じです。
このことを一般の方が口で説明するのは大変です。しかも相手は銀行が2行、農協と郵便局。それぞれ、行くたびに「あれとこれを揃えてください。」と言われるのですが、それぞれに微妙に違っていて混乱するばかり。そこで、私、行政書士へのご依頼です。
新年、明けまして間もなく一ヶ月ですが、来月の第一週で私の事務所の業務もそろそろ落ち着きそうかなという感じです。
農地法等の改正
2010年01月24日
昨日は午後から農地法等の改正についての研修会に参加しました。主催は滋賀県行政書士会土地開発部会です。土地開発部会の皆さん、ご苦労様でした。
さて、私の仕事としての関心は、まず、農地転用許可の基準がどのように変わったかということです。具体的にはミクロの部分で変化があったようですがマクロとしては変化はなさそうです。ただ、「農地転用の規制の厳格化」というふうに銘打っていますから、現場の運用では変化があるかと思います。
農地法による転用許可も、農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域の除外申請も、私有財産権に対する大きな制限であるにもかかわらず、その基準があいまいなので困ることもありますから、気になるところです。
ところで、今回の法改正によって日本の農業が直面している諸問題が解決するのかと言えば、無理っぽいというのが感想です。なかんずく、今もどんどん増えている耕作放棄地の問題の解消には至らないのではないでしょうかね。失業問題が改善しない世の中にあっても魅力ある産業でない農業が、魅力ある産業にならないと耕作放棄地問題の根本的な解決は難しそうです。
そんななか、一般の株式会社、NPO法人など、農業生産法人以外の法人であっても農地を賃借して農業に参入できるようにしたことは影響が大きいのかもしれません。地方の建設業の仕事の減少による余剰労働力の吸収先として農業が注目されるとしたら非常に良い展開になるように思います。
さて、私の仕事としての関心は、まず、農地転用許可の基準がどのように変わったかということです。具体的にはミクロの部分で変化があったようですがマクロとしては変化はなさそうです。ただ、「農地転用の規制の厳格化」というふうに銘打っていますから、現場の運用では変化があるかと思います。
農地法による転用許可も、農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域の除外申請も、私有財産権に対する大きな制限であるにもかかわらず、その基準があいまいなので困ることもありますから、気になるところです。
ところで、今回の法改正によって日本の農業が直面している諸問題が解決するのかと言えば、無理っぽいというのが感想です。なかんずく、今もどんどん増えている耕作放棄地の問題の解消には至らないのではないでしょうかね。失業問題が改善しない世の中にあっても魅力ある産業でない農業が、魅力ある産業にならないと耕作放棄地問題の根本的な解決は難しそうです。
そんななか、一般の株式会社、NPO法人など、農業生産法人以外の法人であっても農地を賃借して農業に参入できるようにしたことは影響が大きいのかもしれません。地方の建設業の仕事の減少による余剰労働力の吸収先として農業が注目されるとしたら非常に良い展開になるように思います。
Posted by 開設者 at
09:15
│Comments(0)
小林繁さん
2010年01月18日
元阪神・巨人の投手、小林繁さんが亡くなられた。57歳って、若いです。小林繁さんといえば、江川ドラフト問題がついて回る。現に、江川氏のコメントがマスコミを賑わせています。望まず切っても切れない関係になった二人です。江川氏によると落ち着いて話せたのはCM撮影のとき1回だけだったようですね。
江川問題の当時、私は大学生で読売新聞の朝刊配達をしていました。それで読むのは読売新聞と報知新聞。読売のオーナーは「正しいことを書いているのは読売と報知だけだ。」と、紙上で話していました。でも、嘘ばっかりだった。そりゃまー、大本営発表ですから仕方がないけど、大新聞でも、こんなもんかと思ったものです。
小林さんも江川氏も結局は被害者じゃなかったかと思いますね。小林さんは説明が要らない被害者。江川氏は、エゴ丸出しの悪い大人に振り回された無知な若者という被害者。江川氏は巨人に入れなければ浪人するつもりだったはず。そこに出て来た「空白の一日」という大人の悪知恵に、半信半疑ながら従ったまでじゃないですかね。
「空白の一日」は、馬鹿な法律家が協約の隙間を見つけ屁理屈を捏ねたことによって生まれたわけです。それを真に受けた読売が、ゴリ押しを通そうとした。(当時も今も読売に振り回される日本プロ野球界の体質は変わっていないですがね。)
「『申し訳ない』という気持ちは、僕の中では終わっていません。原因はこちらにある。小林さんが亡くなったからといって、『申し訳ない』という気持ちは一生なくならないと思います。」という江川氏のコメントが伝わっていますが、特定の人間のエゴが人の一生を左右してしまった悪い例です。十字架を背負ったような江川氏も可哀そうですわ。
それにしても、残念な若い死です。ご冥福を祈ります。
江川問題の当時、私は大学生で読売新聞の朝刊配達をしていました。それで読むのは読売新聞と報知新聞。読売のオーナーは「正しいことを書いているのは読売と報知だけだ。」と、紙上で話していました。でも、嘘ばっかりだった。そりゃまー、大本営発表ですから仕方がないけど、大新聞でも、こんなもんかと思ったものです。
小林さんも江川氏も結局は被害者じゃなかったかと思いますね。小林さんは説明が要らない被害者。江川氏は、エゴ丸出しの悪い大人に振り回された無知な若者という被害者。江川氏は巨人に入れなければ浪人するつもりだったはず。そこに出て来た「空白の一日」という大人の悪知恵に、半信半疑ながら従ったまでじゃないですかね。
「空白の一日」は、馬鹿な法律家が協約の隙間を見つけ屁理屈を捏ねたことによって生まれたわけです。それを真に受けた読売が、ゴリ押しを通そうとした。(当時も今も読売に振り回される日本プロ野球界の体質は変わっていないですがね。)
「『申し訳ない』という気持ちは、僕の中では終わっていません。原因はこちらにある。小林さんが亡くなったからといって、『申し訳ない』という気持ちは一生なくならないと思います。」という江川氏のコメントが伝わっていますが、特定の人間のエゴが人の一生を左右してしまった悪い例です。十字架を背負ったような江川氏も可哀そうですわ。
それにしても、残念な若い死です。ご冥福を祈ります。
松飾り
2010年01月12日
今朝の新聞のコラムにもあったのですが、私も感じていたこと。正月の松飾りをするお家が減ったなぁということです。それに加えて自動車のフロントグリルにしめ縄を付けた車を見ることがほとんどなくなりました。以前は、たくさん付けて走っていた車がありましたけど。
車にしめ縄なんて日本だけの風習だったのでしょうが、まさに日本の正月の風景が減ったと言えるでしょう。かく言う私もあまり付けた記憶がないのですが、私の父の年代の人は几帳面に付けていたような記憶があります。近代的な自動車に昔からの風習のしめ縄。そのマッチングはおもしろかったですがね。
松飾り、しめ縄、日本の正月らしさが、どんどんなくなって行くのは淋しい気もします。逆に暮れのクリスマス時期の家のイルミネーションが増えているような。新しい時代に新しい風習が根付いていくということでしょうか。
車にしめ縄なんて日本だけの風習だったのでしょうが、まさに日本の正月の風景が減ったと言えるでしょう。かく言う私もあまり付けた記憶がないのですが、私の父の年代の人は几帳面に付けていたような記憶があります。近代的な自動車に昔からの風習のしめ縄。そのマッチングはおもしろかったですがね。
松飾り、しめ縄、日本の正月らしさが、どんどんなくなって行くのは淋しい気もします。逆に暮れのクリスマス時期の家のイルミネーションが増えているような。新しい時代に新しい風習が根付いていくということでしょうか。