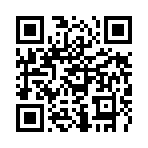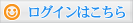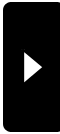行政書士補助者募集
2010年03月31日
根来行政書士事務所では、現在、補助者募集中です。今回は行政書士有資格者希望ですが、将来、行政書士を目指す方も対象とします。
連絡先 根来行政書士事務所 電話077-554-3330
メールnegoro@pearl.ocn.ne.jp
連絡先 根来行政書士事務所 電話077-554-3330
メールnegoro@pearl.ocn.ne.jp
雪桜
再転相続
2010年03月20日
今日の午後は、私の所属する行政書士会の支部の研修会で、テーマは相続遺言でした。一通りの講義のあと、質問時間があり、そこでの質疑応答の中の話題に再転相続のことがありました。
再転相続は、民法916条にあります。『第916条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。』
Aが死亡後、Aの相続人BがAの相続に関して承認も放棄もしないで熟慮期間内に相次いで死亡したというケースです。この場合、Bの相続人CはBの持っていたAの相続を放棄(限定承認)する権利を承継し、Aの遺産の相続に関する放棄(限定承認)を、Cが自己についてBの相続が発生したことを知ったときから単純承認したものとみなされることのない限り、3ケ月内はできます。
この件について、講師はBがその死亡時までに放棄をしていない場合は、もはやCによるAの相続についてのBの放棄はできないというふうに回答されたように聞こえたのですが、そうだとすると、その回答はやはり間違いです。
ただ、今日の質問のケースでは、CもAの共同相続人であるので少しややこしいですが、結論は変わらないでしょう。Bにプラスの財産があり、Aに負債しかない場合、CはまずAの相続に対する自己及びBの放棄を行い、Bの相続について承認すればよろしい。
しかし、ここでCがBの相続(第2相続)について先に放棄をすると、Aの相続を放棄(限定承認)する権利をも承継しないことになって、もはやCはBの第1相続についての放棄をすることはできません。(C固有の第1相続の放棄は熟慮期間内である限りできます。)
今日の事例では、BがAの死亡保険金を得たのちに相続放棄せずに死亡したということだったと思いますが、死亡保険金は相続の対象にならないので相続放棄しても受領できます。
ひょっとしたら、質問者の事例ではBの死亡時期がBの熟慮期間経過後だったかもしれず、そうなると結論は大きく変わってしまいます。数次相続の場合や代襲相続のケースでは、死亡の順序が結論を大きく左右するので、注意が必要です。
再転相続は、民法916条にあります。『第916条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。』
Aが死亡後、Aの相続人BがAの相続に関して承認も放棄もしないで熟慮期間内に相次いで死亡したというケースです。この場合、Bの相続人CはBの持っていたAの相続を放棄(限定承認)する権利を承継し、Aの遺産の相続に関する放棄(限定承認)を、Cが自己についてBの相続が発生したことを知ったときから単純承認したものとみなされることのない限り、3ケ月内はできます。
この件について、講師はBがその死亡時までに放棄をしていない場合は、もはやCによるAの相続についてのBの放棄はできないというふうに回答されたように聞こえたのですが、そうだとすると、その回答はやはり間違いです。
ただ、今日の質問のケースでは、CもAの共同相続人であるので少しややこしいですが、結論は変わらないでしょう。Bにプラスの財産があり、Aに負債しかない場合、CはまずAの相続に対する自己及びBの放棄を行い、Bの相続について承認すればよろしい。
しかし、ここでCがBの相続(第2相続)について先に放棄をすると、Aの相続を放棄(限定承認)する権利をも承継しないことになって、もはやCはBの第1相続についての放棄をすることはできません。(C固有の第1相続の放棄は熟慮期間内である限りできます。)
今日の事例では、BがAの死亡保険金を得たのちに相続放棄せずに死亡したということだったと思いますが、死亡保険金は相続の対象にならないので相続放棄しても受領できます。
ひょっとしたら、質問者の事例ではBの死亡時期がBの熟慮期間経過後だったかもしれず、そうなると結論は大きく変わってしまいます。数次相続の場合や代襲相続のケースでは、死亡の順序が結論を大きく左右するので、注意が必要です。
成年後見
2010年03月18日
今日の午後は、行政書士会の成年後見に関する研修会。今日の研修の半分は研修会というより、これから動き出す行政書士による成年後見事業の説明会という感じでした。 残りの半分は講師の実体験をもとにしたお話で、こちらは、たいへんさ加減が伝わる机上の空論ではないお話しで迫力がありました。
医療技術の進歩などで、どんどん長生きする世の中、高齢者社会に伴い意思表示を自分でできなくなったときにどうなるか?(もちろん、そういう事態は高齢になってからとは限らないのですが。)誰しも長生きすれば来るやもしれない将来ですから、無関心ではおれません。
動き出す行政書士の後見事業。しかし、月一回、10か月に及ぶ研修への参加。そして、実務への対応。私に出来るかどうか不安で、直ぐに参加しますとは言い難いのが偽らざるところです。けれども、行政書士界としては新しい潮流と言えそうな事業だけに、そういう意味でも無関心ではおれません。
新しい潮流というのは、今日の研修会の参加者を拝見していても、ベテランが少ないのでそう思いました。新しい時代に新しい取り組み、そして新しい人。行政書士界の活性化のためには、これは良いことですね。
また、この成年後見に関する限り、手続きうんぬんというより、後見等を受ける人を中心とした人間関係が大変だと思います。だから、裁判所での手続きを誰がするかというようなことは小さなことです。なのに、そんなとこにも縄張り争いを持ち込むなんて、愚の骨頂です。
それはさておき、私も過去、親族後見のお手伝いを2件したことがあります。いずれも、入所された施設での費用を捻出するために被後見人の自宅を売却することが主たる目的でした。と、言えば誤解されると聞こえが悪くないでもないですが、家族にとっては切実な問題でした。
そんなおり、昨日のこのニュース。「成年後見人の着服急増、財産管理の意識薄く」
悪気がないケースもけっこう多いのではないかと思ったりしますし、家庭裁判所でも選任して、しっぱなしでは、法律や制度に疎い親族後見人には、勘違いする人がいても仕方がないかなと思ったりします。
医療技術の進歩などで、どんどん長生きする世の中、高齢者社会に伴い意思表示を自分でできなくなったときにどうなるか?(もちろん、そういう事態は高齢になってからとは限らないのですが。)誰しも長生きすれば来るやもしれない将来ですから、無関心ではおれません。
動き出す行政書士の後見事業。しかし、月一回、10か月に及ぶ研修への参加。そして、実務への対応。私に出来るかどうか不安で、直ぐに参加しますとは言い難いのが偽らざるところです。けれども、行政書士界としては新しい潮流と言えそうな事業だけに、そういう意味でも無関心ではおれません。
新しい潮流というのは、今日の研修会の参加者を拝見していても、ベテランが少ないのでそう思いました。新しい時代に新しい取り組み、そして新しい人。行政書士界の活性化のためには、これは良いことですね。
また、この成年後見に関する限り、手続きうんぬんというより、後見等を受ける人を中心とした人間関係が大変だと思います。だから、裁判所での手続きを誰がするかというようなことは小さなことです。なのに、そんなとこにも縄張り争いを持ち込むなんて、愚の骨頂です。
それはさておき、私も過去、親族後見のお手伝いを2件したことがあります。いずれも、入所された施設での費用を捻出するために被後見人の自宅を売却することが主たる目的でした。と、言えば誤解されると聞こえが悪くないでもないですが、家族にとっては切実な問題でした。
そんなおり、昨日のこのニュース。「成年後見人の着服急増、財産管理の意識薄く」
悪気がないケースもけっこう多いのではないかと思ったりしますし、家庭裁判所でも選任して、しっぱなしでは、法律や制度に疎い親族後見人には、勘違いする人がいても仕方がないかなと思ったりします。
タグ :成年後見
Posted by 開設者 at
21:20
│Comments(0)
今年も道に迷ったe-tax
2010年03月16日
昨日は、確定申告の最終日でした。会計ソフトで作った決算書類は土曜日には出来上がっていたので、昨日の朝、電子申告手続きをしようとしたまでは良かったのですが、国税庁のホームページを開けて、またもや迷路に入ってしまいました。
「確定申告特集」でウロチョロ。「申告・納税手続」でウロチョロ。なかなか、お目当てのところに辿りつきません。焦る、焦る。焦ると、いよいよ深みに嵌っていくような気すらします。ウロチョロすること約1時間。
うわー、こりゃ今日中にはできないかもしれんし、税務署に紙ベースで持って行こうかなと思い始めたとき、思いだしたのです。何を思い出したかというと、去年、このブログで国税庁のHPの案内の解り難さについて、ブー垂れたことを。
去年のブログがこちら。これが役に立ったのです。そして、今年も見事に去年と同じ間違いを犯して、迷路の森の奥深くを彷徨っていたのです。
もう、こうなるとお笑いですが、1年に1回しかしないことなので、仕方がないと自らを慰めながら、ついに送信できた!と思ったらエラーメッセージが却ってきました。何なんと思って、エラーメッセージを読むと「電子証明書が未登録、又は登録された電子証明書と一致しません。」と。
でも、これは解りましたよ、去年10月に電子証明書を更新したため、去年、電子申告したときとは違っていたのです。電子証明書の登録をやりなおして、再送!これにて、一件落着。
間違えさえしなければ、非常に簡単な電子申告なのですが、来年もまた間違うだろうから、手順を紙に書いて保存しておきます。しかし、このブログが思わぬところで役立ったにもんです。
「確定申告特集」でウロチョロ。「申告・納税手続」でウロチョロ。なかなか、お目当てのところに辿りつきません。焦る、焦る。焦ると、いよいよ深みに嵌っていくような気すらします。ウロチョロすること約1時間。
うわー、こりゃ今日中にはできないかもしれんし、税務署に紙ベースで持って行こうかなと思い始めたとき、思いだしたのです。何を思い出したかというと、去年、このブログで国税庁のHPの案内の解り難さについて、ブー垂れたことを。
去年のブログがこちら。これが役に立ったのです。そして、今年も見事に去年と同じ間違いを犯して、迷路の森の奥深くを彷徨っていたのです。
もう、こうなるとお笑いですが、1年に1回しかしないことなので、仕方がないと自らを慰めながら、ついに送信できた!と思ったらエラーメッセージが却ってきました。何なんと思って、エラーメッセージを読むと「電子証明書が未登録、又は登録された電子証明書と一致しません。」と。
でも、これは解りましたよ、去年10月に電子証明書を更新したため、去年、電子申告したときとは違っていたのです。電子証明書の登録をやりなおして、再送!これにて、一件落着。
間違えさえしなければ、非常に簡単な電子申告なのですが、来年もまた間違うだろうから、手順を紙に書いて保存しておきます。しかし、このブログが思わぬところで役立ったにもんです。