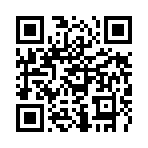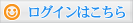起業の技術
2013年12月30日
起業を考えている人が、「お正月に読むんだったら、これかも!」という本のご紹介です。これから起業する人や、既に起業したけど、こういう勉強はしていないという人に、最適な起業の基本書的な本だと思います。
『起業の技術』浜口隆則 著
著者曰く、「10年以内には90%の起業が失敗しています」
その現実を踏まえ、この本は、それでも起業する人に準備を怠らず、事業を成功させるために「何が必要なのか」 「明日から何をすべきか」というところを基本から教えてくれます。
しかも、小難しい理論はあまりなく、スラスラ読めます。
それでいて、内容は、経営とは何かに始まって、経営戦略、マーケティング、集客ノウハウ、見込み客のフォロー、クロージング、そして、経理・財務、組織構築その他、経営者が知っておくべき基本を網羅するものになっている良書だと思います。
もちろん、これだけ知っていれば成功できるというようなものではないですが、基本的なことが良く整理できていて、これらの基礎的な情報を知って起業をするのと知らずにするのとでは、かなり違うでしょう。
そもそも経営の基本的なところは、実は、シンプルなものではないかと私は考えています。
でも、シンプルであることと、実践やその継続が容易というのとは話の次元が違う訳で、理屈はシンプルだが実行と継続は難しい。それが事業で成功することの難しさになっているのだと、私は思うのです。
ゆえに、シンプルな基本をいつも意識して実践する、継続する。
そして、途中で迷ったら基本に立ち戻る。その戻るべき原点と言うべき基本を知っていることは非常に大切ですよね。
そういう意味でも、既に開業している私のような者にとっても読むに値する本だと思った次第です。
『起業の技術』浜口隆則 著
著者曰く、「10年以内には90%の起業が失敗しています」
その現実を踏まえ、この本は、それでも起業する人に準備を怠らず、事業を成功させるために「何が必要なのか」 「明日から何をすべきか」というところを基本から教えてくれます。
しかも、小難しい理論はあまりなく、スラスラ読めます。
それでいて、内容は、経営とは何かに始まって、経営戦略、マーケティング、集客ノウハウ、見込み客のフォロー、クロージング、そして、経理・財務、組織構築その他、経営者が知っておくべき基本を網羅するものになっている良書だと思います。
もちろん、これだけ知っていれば成功できるというようなものではないですが、基本的なことが良く整理できていて、これらの基礎的な情報を知って起業をするのと知らずにするのとでは、かなり違うでしょう。
そもそも経営の基本的なところは、実は、シンプルなものではないかと私は考えています。
でも、シンプルであることと、実践やその継続が容易というのとは話の次元が違う訳で、理屈はシンプルだが実行と継続は難しい。それが事業で成功することの難しさになっているのだと、私は思うのです。
ゆえに、シンプルな基本をいつも意識して実践する、継続する。
そして、途中で迷ったら基本に立ち戻る。その戻るべき原点と言うべき基本を知っていることは非常に大切ですよね。
そういう意味でも、既に開業している私のような者にとっても読むに値する本だと思った次第です。
遺言と遺書は違います
2013年12月25日
昨日、紛争の火種になることが多い法定相続よりも、遺言による相続が増えたほうが良いという趣旨のことを書きました。
その中で、「遺言というと何だか縁起が悪いとか、死ぬのを待たれているようだとかいうような考えに囚われてタブーのように思われる人」もあると書いたのですが、その原因について、いろいろ考えた中で、
どうも、一般に遺言と遺書が混同されたり、あるいはイメージとしてダブってしまっているのではないかという思いが大きくなりました。
次は、ウィキペディアの「遺言」の冒頭の引用です。
『遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。このうち民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。法律用語としてはいごんと読まれることが多い。』
次が、ウィキペディアの「遺書」の冒頭の引用です。
『遺書(いしょ)は自殺する人、又は死ぬことが確実な人が残す文章である。』
しかも、遺書のページには、「財産分与などの法律的な問題を記す「遺言書」とは異なります。」と、わざわざ書いてあります。
これは、一般に遺言と遺書が混同されたり、あるいはイメージとしてダブってしまっている怖れがあるから、わざわざ書いてあるのでしょう。
遺言の上記説明のなかにもあるように、遺言も遺書も「広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章」と、とらえると同じであり、この二つを混同されるのも無理はないと思います。
そして、その結果、遺言も遺書と同じく自殺する人、又は死ぬことが確実な人が書くものと誤解されたら、そりゃ、遺言も忌み嫌われるべきものというイメージになってしまいますよね。
でも、遺書のページに注意書きされているように、遺書と財産分与などの法律的な問題を記す遺言「書」とは根本的に違います。
自分の財産を自分が使えなくなったとき(死後)、その財産をどのようにして欲しいかという意思(又は遺志)を法律的に有効なものとして表すのが遺言です。
それは、誰か好きな人に何かプレゼントする、ご先祖から承継してきたものを特定の人に託すといった、財産上の法的処分行為です。(遺言でなしうることは、このほかにもありますが、ここでは割愛します。)
相続の法定事項は、被相続人の意思によって修正することができる、そこには民事法の原則である私的自治の考え方があらわれているのです。
被相続人にとって遺す財産は、すなわち相続人が受け取る財産です。
相続は私が死んだあとのことで、相続人が考えることとか、法律で決まっていることと思っている人がいるかもしれません。
でも、「後は野となれ山となれ、私の死んだあとのことは知ったことじゃない。」と、本当に考えている人は、どちらかと言えば少ないのではないでしょうか。
被相続人と関係の深い相続人が困るようなことがないように配慮すべきはマナーであり、思いやりであるというような意識が一般に広まることを期待したいものです。
そのために、遺言なき相続が、実はやっかいなものであるということと、一方で、問題のある遺言によって、かえってトラブルが起こることもあることをも併せて、理解してもらうために私も情報発信していきたいと考えています。
その中で、「遺言というと何だか縁起が悪いとか、死ぬのを待たれているようだとかいうような考えに囚われてタブーのように思われる人」もあると書いたのですが、その原因について、いろいろ考えた中で、
どうも、一般に遺言と遺書が混同されたり、あるいはイメージとしてダブってしまっているのではないかという思いが大きくなりました。
次は、ウィキペディアの「遺言」の冒頭の引用です。
『遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。このうち民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。法律用語としてはいごんと読まれることが多い。』
次が、ウィキペディアの「遺書」の冒頭の引用です。
『遺書(いしょ)は自殺する人、又は死ぬことが確実な人が残す文章である。』
しかも、遺書のページには、「財産分与などの法律的な問題を記す「遺言書」とは異なります。」と、わざわざ書いてあります。
これは、一般に遺言と遺書が混同されたり、あるいはイメージとしてダブってしまっている怖れがあるから、わざわざ書いてあるのでしょう。
遺言の上記説明のなかにもあるように、遺言も遺書も「広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章」と、とらえると同じであり、この二つを混同されるのも無理はないと思います。
そして、その結果、遺言も遺書と同じく自殺する人、又は死ぬことが確実な人が書くものと誤解されたら、そりゃ、遺言も忌み嫌われるべきものというイメージになってしまいますよね。
でも、遺書のページに注意書きされているように、遺書と財産分与などの法律的な問題を記す遺言「書」とは根本的に違います。
自分の財産を自分が使えなくなったとき(死後)、その財産をどのようにして欲しいかという意思(又は遺志)を法律的に有効なものとして表すのが遺言です。
それは、誰か好きな人に何かプレゼントする、ご先祖から承継してきたものを特定の人に託すといった、財産上の法的処分行為です。(遺言でなしうることは、このほかにもありますが、ここでは割愛します。)
相続の法定事項は、被相続人の意思によって修正することができる、そこには民事法の原則である私的自治の考え方があらわれているのです。
被相続人にとって遺す財産は、すなわち相続人が受け取る財産です。
相続は私が死んだあとのことで、相続人が考えることとか、法律で決まっていることと思っている人がいるかもしれません。
でも、「後は野となれ山となれ、私の死んだあとのことは知ったことじゃない。」と、本当に考えている人は、どちらかと言えば少ないのではないでしょうか。
被相続人と関係の深い相続人が困るようなことがないように配慮すべきはマナーであり、思いやりであるというような意識が一般に広まることを期待したいものです。
そのために、遺言なき相続が、実はやっかいなものであるということと、一方で、問題のある遺言によって、かえってトラブルが起こることもあることをも併せて、理解してもらうために私も情報発信していきたいと考えています。
配偶者貢献に応じ遺産分割=法務省、年明け検討開始
2013年12月24日
配偶者貢献に応じ遺産分割=法務省、年明け検討開始
法務省が、遺産分割に当たり家事や育児など配偶者の貢献度を反映させるため、民法改正を含む法整備の検討に着手する方針を決めたそうです。
内容を見てみないとなんとも言えませんが、相続紛争が増加する中、根本的な問題として法律による相続を中心とするのではなく、遺言による相続を中心とする考え方を一般に浸透させるほうが良いように思います。
法律で決めようとしても、相続に関する事情が個々に違うわけで、それを法律でコントロールしようとするのには自ずと限界があります。
個々の相続に関する事情については、通常、当該相続の被相続人(予定者)が解っているわけですから、その事情を当該相続にできるだけ反映させるには遺言によって相続の内容を決めるのが、紛争予防の観点からベストだと私は思うのです。
遺言というと何だか縁起が悪いとか、死ぬのを待たれているようだとかいうような考えに囚われてタブーのように思われる人もありますが、外国では遺言を遺さずに死ぬのを恥とするところもあるようです。
自分の遺産の処分は自分で決める。そして、紛争予防の観点から、遺された遺族がいわゆる争続などで苦しまないようにするということを中心に考える必要があるのではないでしょうか。
そのために、遺言の暗いイメージを払しょくし、遺言作成をもっと普及させるべく、啓発活動を行うべきです。
相続は民事ですから、当事者の処分権を尊重し、法律はあくまでバックアップに回って、若くして亡くなるとかいったやむを得ない事情の際に持ち出されるようにすべきと私は考えます。
法務省が、遺産分割に当たり家事や育児など配偶者の貢献度を反映させるため、民法改正を含む法整備の検討に着手する方針を決めたそうです。
内容を見てみないとなんとも言えませんが、相続紛争が増加する中、根本的な問題として法律による相続を中心とするのではなく、遺言による相続を中心とする考え方を一般に浸透させるほうが良いように思います。
法律で決めようとしても、相続に関する事情が個々に違うわけで、それを法律でコントロールしようとするのには自ずと限界があります。
個々の相続に関する事情については、通常、当該相続の被相続人(予定者)が解っているわけですから、その事情を当該相続にできるだけ反映させるには遺言によって相続の内容を決めるのが、紛争予防の観点からベストだと私は思うのです。
遺言というと何だか縁起が悪いとか、死ぬのを待たれているようだとかいうような考えに囚われてタブーのように思われる人もありますが、外国では遺言を遺さずに死ぬのを恥とするところもあるようです。
自分の遺産の処分は自分で決める。そして、紛争予防の観点から、遺された遺族がいわゆる争続などで苦しまないようにするということを中心に考える必要があるのではないでしょうか。
そのために、遺言の暗いイメージを払しょくし、遺言作成をもっと普及させるべく、啓発活動を行うべきです。
相続は民事ですから、当事者の処分権を尊重し、法律はあくまでバックアップに回って、若くして亡くなるとかいったやむを得ない事情の際に持ち出されるようにすべきと私は考えます。