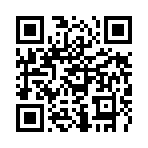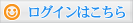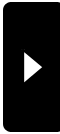遺産分割の話し合いが着く前でも預金の一部の引き出しが可能に
2019年01月09日
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO38936780U8A211C1000000?type=my&fbclid=IwAR12CoaQeHep3M1yGDDhDCATydsBjHe4039UDn4HrWoAqlnqe5-YLbhm2Tg
預貯金の遺産分割前の払戻し制度が創設されます。
人が亡くなると、その人の預貯金の口座が凍結(ロック)されて引き出しが出来なくなるということは、一般に知られることになっていました。ですんで、亡くなる前におろしておけとか。
でも、この直前の引き出しや凍結がもとで、相続の紛争に発展したり、金融機関ともめたりといった混乱もありました。
そもそも金融機関との、もめ事の元凶は、「預貯金は相続開始と同時に分割されているもんね。だから、その分は一人で払い戻してもらえるよ。」という裁判所の判断にあったわけですが、
でも、金融機関としては、「そんなことして相続人の一人に払い戻したら他の相続人からクレームがついて二重払いさせられたらいやだもんね。」と拒否されることが普通でした。
ところが、平成28年に、裁判所の判断が変わって、「やっぱり皆のハンコが揃わないとあかんわ。」ということに成ってしまいました。
それでは、葬儀費用の支払いに、はたまた、亡くなった人に養われていた人がたちまち生活費がなくて、困るということで、裁判所を通さない簡易な方法として、次のような預貯金の一部の払い戻し制度が創設されます。
『各共同相続人は、遺産の預貯金債権のうち、各口座ごとに以下の計算式による額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、150万円が限度。)までについては、他の相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができる。』
【計算式】
単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める相続人の法定相続分)
結局、初めの記事にある、例えで言えば
相続人が長男と次男の2人の場合で、両者の法定相続分は2分の1で、遺産が預金のみ(1つの金融機関で1口座のみ)1000万円だとすると各人のその相続分は500万円。
その3分の1は約166万円ですが、1つの金融機関に対しては150万が限度となってますから、この場合、相続人の一人につき150万が払い戻しを受けられる限度額になります。
なお、この制度は2019年7月1日から始まりますが、それ以前に開始した相続についても、2019年7月1日以後に金融機関に払い戻し請求する場合は適用されます。
ただ、特にこの制度の開始当初は金融機関の窓口の対応は慎重で時間がかかりそうですが、はたしてどうなるでしょうか。
預貯金の遺産分割前の払戻し制度が創設されます。
人が亡くなると、その人の預貯金の口座が凍結(ロック)されて引き出しが出来なくなるということは、一般に知られることになっていました。ですんで、亡くなる前におろしておけとか。
でも、この直前の引き出しや凍結がもとで、相続の紛争に発展したり、金融機関ともめたりといった混乱もありました。
そもそも金融機関との、もめ事の元凶は、「預貯金は相続開始と同時に分割されているもんね。だから、その分は一人で払い戻してもらえるよ。」という裁判所の判断にあったわけですが、
でも、金融機関としては、「そんなことして相続人の一人に払い戻したら他の相続人からクレームがついて二重払いさせられたらいやだもんね。」と拒否されることが普通でした。
ところが、平成28年に、裁判所の判断が変わって、「やっぱり皆のハンコが揃わないとあかんわ。」ということに成ってしまいました。
それでは、葬儀費用の支払いに、はたまた、亡くなった人に養われていた人がたちまち生活費がなくて、困るということで、裁判所を通さない簡易な方法として、次のような預貯金の一部の払い戻し制度が創設されます。
『各共同相続人は、遺産の預貯金債権のうち、各口座ごとに以下の計算式による額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、150万円が限度。)までについては、他の相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができる。』
【計算式】
単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める相続人の法定相続分)
結局、初めの記事にある、例えで言えば
相続人が長男と次男の2人の場合で、両者の法定相続分は2分の1で、遺産が預金のみ(1つの金融機関で1口座のみ)1000万円だとすると各人のその相続分は500万円。
その3分の1は約166万円ですが、1つの金融機関に対しては150万が限度となってますから、この場合、相続人の一人につき150万が払い戻しを受けられる限度額になります。
なお、この制度は2019年7月1日から始まりますが、それ以前に開始した相続についても、2019年7月1日以後に金融機関に払い戻し請求する場合は適用されます。
ただ、特にこの制度の開始当初は金融機関の窓口の対応は慎重で時間がかかりそうですが、はたしてどうなるでしょうか。
年の初めの会社設立
2018年01月07日

2018年の最初のお仕事は合同会社の設立申請でした!
合同会社は比較的、簡単に作れます。公証人の認証も不要、電子署名による電子定款なら、印紙税4万円も不要。登録免許税も株式会社15万に対して6万円と9万円も少なくて済みます。
けれども、税金面でのメリットは株式会社と変わりません。変わるとすると、少し一般には見慣れないマイナーな会社なので、社名を前面に出して営業する必要があるとすると、ちょっと、心配かも・・・。
でも、今回は、資産管理を目的とするプライベートカンパニーなので、まったく、問題なーし!
そこで、合同会社の定款についてネット上では、誰でもかんたんとか、穴埋めするだけで作れる雛形とか、たくさん出て来ます。
でも、安易に作ると、困ったことになる場合も。たとえば、
会社法上、合同会社には「解散の事由」が定められていて「社員が欠けたこと(1人もいなくなったこと)」により解散します。
社員1人の場合であれば、その社員の死亡により合同会社が解散してしまうことになるのです。社員1人で死亡した場合、残念ながら合同会社を存続させる方法はありません。
いきなり事業ができなくなることは、家族はもちろん第三者にも多大な影響を与えかねません。
そこで、予め定款に持分承継の規定を置くことによって、相続人が社員の持分を相続することができるようになります。
その条項が、次
(相続及び合併による持分の承継)
第○条 当会社社員が死亡した場合または合併により消滅した場合には、当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する。
このように定めることによって、相続人が死亡した社員の持分を相続することができるようになります。もしこの規定がなければ、解散されてしまいますので注意しましょう。
その他、簡単に出来る合同会社とは言え、やはり、一度は専門家に相談することをお奨めします。
なにせ、電子定款の作成を行政書士などに頼めば印紙代4万円が不要で、それプラス少々の費用で、専門家の知恵が得られるのですから。お得感、ありありですよ。
滋賀県行政書士会湖南支部の無料相談会
2016年08月16日
滋賀県行政書士会湖南支部では、野洲市・栗東市・草津市・守山市の各市で月1回、無料相談会を実施しています。
お住まいの市の相談会場をご確認の上、お申し込み先までご予約をお願い致します。
各会場でお待ちしておりますので、お気軽にお越しください。
詳細につきましては、下記のアドレスをクリックして頂き、ご確認願います。
http://www.gyosei-konan.jp/%e7%84%a1%e6%96%99%e7%9b%b8%e8%ab%87%e4%bc%9a/
お住まいの市の相談会場をご確認の上、お申し込み先までご予約をお願い致します。
各会場でお待ちしておりますので、お気軽にお越しください。
詳細につきましては、下記のアドレスをクリックして頂き、ご確認願います。
http://www.gyosei-konan.jp/%e7%84%a1%e6%96%99%e7%9b%b8%e8%ab%87%e4%bc%9a/
親族間不動産売買の住宅ローン
2014年11月06日
7月から私の事務所で取り組んでいました、親族間での不動産売買に関する住宅ローンの承認が先ごろ出ました。
そもそも親族間での不動産売買では住宅ローンを借り入れすることが、一つの難関であるのですが、
今回は、競売、リースバック、買い戻しということで、かなり難度の高い案件でした。
承認が出たことで、ホッとしています。あとは決済の段取りをするだけです。
競売や任意売却の後、リースバックで不動産に住み続けるというパターンは、かなり一般化してきていますので、
決して、珍しいお話ではなくなってきていると言えますが、その後、買い戻すというときに、問題になるのが住宅ローンです。
一般に金融機関では、この種の案件を嫌っていますので。
もし、このようなケースでお困りの方がありましたら、一度、当事務所にご相談ください。
親族間の不動産売買での住宅ローンについては、こちらもご参考にしていただければと存じます⇒親族間売買と融資
そもそも親族間での不動産売買では住宅ローンを借り入れすることが、一つの難関であるのですが、
今回は、競売、リースバック、買い戻しということで、かなり難度の高い案件でした。
承認が出たことで、ホッとしています。あとは決済の段取りをするだけです。
競売や任意売却の後、リースバックで不動産に住み続けるというパターンは、かなり一般化してきていますので、
決して、珍しいお話ではなくなってきていると言えますが、その後、買い戻すというときに、問題になるのが住宅ローンです。
一般に金融機関では、この種の案件を嫌っていますので。
もし、このようなケースでお困りの方がありましたら、一度、当事務所にご相談ください。
親族間の不動産売買での住宅ローンについては、こちらもご参考にしていただければと存じます⇒親族間売買と融資
ご依頼者様から嬉しい「お客様の声」を頂きました!(任意売却)
2014年04月01日
当事務所でご自宅の任意売却のお手伝いをさせて頂いたお客様から、嬉しい「お客様の声」を頂きましたので、ご紹介させて頂きます。
なお、内容は全て原文のままですが、氏名・住所等個人が特定される情報は伏せさせて頂きます。
**************************
お客様 滋賀県在住 T様
Q 根来行政書士事務所に依頼をする前に、どんなことで悩んでいましたか?
A 住宅ローンの返済が滞り、不動産の任意売却の方法がわからなく悩んでいた。
Q 根来行政書士事務所を知って、すぐ依頼しようとしましたか?しなかったとしたら、なぜですか?
A 途中、不動産会社に依頼したが、なかなか進まなかった。
Q 何が決め手となって根来行政書士事務所に依頼しましたか?
A 根来さんのお話を聞いて。
Q 実際に根来行政書士事務所に依頼してみて、いかがでしたか?
A 本当に良かったと思っています。任意売却、出来、本当にありがとうございました。
**************************
このようなお声を頂くと、背筋がピンと伸びる思いと同時に、困っておられる方のために、もっと頑張らねばと思います。
このようなお声を下さったT様に改めて感謝したいと思います。
住宅ローンのご返済でお悩みの方は、是非、下記サイトを一度ご覧ください!
「行政書士が不動産の任意売却の無料相談をお受けします」
http://ninbai.tetuzuki.info/
なお、内容は全て原文のままですが、氏名・住所等個人が特定される情報は伏せさせて頂きます。
**************************
お客様 滋賀県在住 T様
Q 根来行政書士事務所に依頼をする前に、どんなことで悩んでいましたか?
A 住宅ローンの返済が滞り、不動産の任意売却の方法がわからなく悩んでいた。
Q 根来行政書士事務所を知って、すぐ依頼しようとしましたか?しなかったとしたら、なぜですか?
A 途中、不動産会社に依頼したが、なかなか進まなかった。
Q 何が決め手となって根来行政書士事務所に依頼しましたか?
A 根来さんのお話を聞いて。
Q 実際に根来行政書士事務所に依頼してみて、いかがでしたか?
A 本当に良かったと思っています。任意売却、出来、本当にありがとうございました。
**************************
このようなお声を頂くと、背筋がピンと伸びる思いと同時に、困っておられる方のために、もっと頑張らねばと思います。
このようなお声を下さったT様に改めて感謝したいと思います。
住宅ローンのご返済でお悩みの方は、是非、下記サイトを一度ご覧ください!
「行政書士が不動産の任意売却の無料相談をお受けします」
http://ninbai.tetuzuki.info/