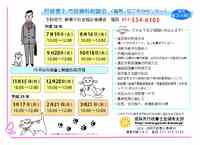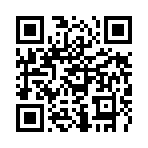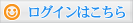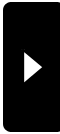再転相続
2010年03月20日
今日の午後は、私の所属する行政書士会の支部の研修会で、テーマは相続遺言でした。一通りの講義のあと、質問時間があり、そこでの質疑応答の中の話題に再転相続のことがありました。
再転相続は、民法916条にあります。『第916条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。』
Aが死亡後、Aの相続人BがAの相続に関して承認も放棄もしないで熟慮期間内に相次いで死亡したというケースです。この場合、Bの相続人CはBの持っていたAの相続を放棄(限定承認)する権利を承継し、Aの遺産の相続に関する放棄(限定承認)を、Cが自己についてBの相続が発生したことを知ったときから単純承認したものとみなされることのない限り、3ケ月内はできます。
この件について、講師はBがその死亡時までに放棄をしていない場合は、もはやCによるAの相続についてのBの放棄はできないというふうに回答されたように聞こえたのですが、そうだとすると、その回答はやはり間違いです。
ただ、今日の質問のケースでは、CもAの共同相続人であるので少しややこしいですが、結論は変わらないでしょう。Bにプラスの財産があり、Aに負債しかない場合、CはまずAの相続に対する自己及びBの放棄を行い、Bの相続について承認すればよろしい。
しかし、ここでCがBの相続(第2相続)について先に放棄をすると、Aの相続を放棄(限定承認)する権利をも承継しないことになって、もはやCはBの第1相続についての放棄をすることはできません。(C固有の第1相続の放棄は熟慮期間内である限りできます。)
今日の事例では、BがAの死亡保険金を得たのちに相続放棄せずに死亡したということだったと思いますが、死亡保険金は相続の対象にならないので相続放棄しても受領できます。
ひょっとしたら、質問者の事例ではBの死亡時期がBの熟慮期間経過後だったかもしれず、そうなると結論は大きく変わってしまいます。数次相続の場合や代襲相続のケースでは、死亡の順序が結論を大きく左右するので、注意が必要です。
再転相続は、民法916条にあります。『第916条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。』
Aが死亡後、Aの相続人BがAの相続に関して承認も放棄もしないで熟慮期間内に相次いで死亡したというケースです。この場合、Bの相続人CはBの持っていたAの相続を放棄(限定承認)する権利を承継し、Aの遺産の相続に関する放棄(限定承認)を、Cが自己についてBの相続が発生したことを知ったときから単純承認したものとみなされることのない限り、3ケ月内はできます。
この件について、講師はBがその死亡時までに放棄をしていない場合は、もはやCによるAの相続についてのBの放棄はできないというふうに回答されたように聞こえたのですが、そうだとすると、その回答はやはり間違いです。
ただ、今日の質問のケースでは、CもAの共同相続人であるので少しややこしいですが、結論は変わらないでしょう。Bにプラスの財産があり、Aに負債しかない場合、CはまずAの相続に対する自己及びBの放棄を行い、Bの相続について承認すればよろしい。
しかし、ここでCがBの相続(第2相続)について先に放棄をすると、Aの相続を放棄(限定承認)する権利をも承継しないことになって、もはやCはBの第1相続についての放棄をすることはできません。(C固有の第1相続の放棄は熟慮期間内である限りできます。)
今日の事例では、BがAの死亡保険金を得たのちに相続放棄せずに死亡したということだったと思いますが、死亡保険金は相続の対象にならないので相続放棄しても受領できます。
ひょっとしたら、質問者の事例ではBの死亡時期がBの熟慮期間経過後だったかもしれず、そうなると結論は大きく変わってしまいます。数次相続の場合や代襲相続のケースでは、死亡の順序が結論を大きく左右するので、注意が必要です。
Posted by 開設者 at 19:17│Comments(0)
│相続・遺言
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。