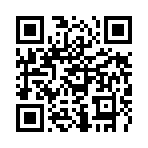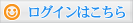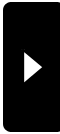保証協会の代位弁済
2012年09月04日
小企業の金融機関取引は、日本政策金融公庫と信用保証協会との関係が切っても切れないと言えるでしょう。それくらいお世話になることが多い両者ですが、日本政策金融公庫と信用保証協会とでは、取引の内容に違いがあります。
日本政策金融公庫と小企業は主に直接、貸主と借主の関係に立ちますが、信用保証協会は小企業が市中の金融機関から借入をする場合に、あくまで保証するだけです。
ですから、信用保証協会を利用する場合は、保証料が必要になるわけですね。けっこう、この保証料が馬鹿にならないんですが。
それはさておき、先に、このブログで、「中小企業金融円滑化法がH25年3月で終了することに伴って、金融機関は返済猶予の継続に応じない企業に対しては、当初の返済額での返済を要求し返済不能となれば、期限の利益喪失によって、保証協会の代位弁済やサービサー等への債権売却へと進むことになるでしょう。」と、書きました。
通常、金融機関との約定の弁済がなされず期限の利益が喪失となってから、90日(一部の協会は60日)を経過すると、金融機関は保証協会に対して代位弁済の請求ができます。
保証協会が金融機関に対して代位弁済すると、保証協会が債務者に対して求償権を取得することになります。ですから、代位弁済以後は、返済の交渉相手が金融機関から保証協会に変わるということです。
事態がここまで進んだ場合、企業としては新たな借り入れは困難になりますが、担保不動産の処分等を通じて返済できる分は返済し、残った債務をコツコツと返すことによって再起を図ることができるという考え方もあります。
この場合、商品仕入や外注費や給料などは、すべて自己資金で決済することになりますので、手元資金の確保が絶対に必要になりますから、さまざまな困難がついてまわることが予想されますが、「期限の利益喪失」や「代位弁済」が、即、倒産につながるわけではないことだけは必ず経営者として理解しておきましょう。
特に、リ・スケジュールで資金繰りが出来ていた企業は、代位弁済後も状況的には、さほど変わらないはずです。担保不動産の処分その他出来る限りの弁済について、誠意をもって保証協会に対応すれば、協会が強硬なことを言い出す可能性は低いですから、落ち着いて対応することが肝要です。
なお、【倒産を回避して再起を図るなら、担保不動産の処分は競売は回避し可能な限り高値で出来るようにするべきです。】←これは大きなポイントです。
事業再生には、法律、金融取引、不動産流通、税金の知識が不可欠です。偏った知識で対応すると結果的に損をすることや挫折することも多々あります。ぜひ、専門家にご相談ください。
日本政策金融公庫と小企業は主に直接、貸主と借主の関係に立ちますが、信用保証協会は小企業が市中の金融機関から借入をする場合に、あくまで保証するだけです。
ですから、信用保証協会を利用する場合は、保証料が必要になるわけですね。けっこう、この保証料が馬鹿にならないんですが。
それはさておき、先に、このブログで、「中小企業金融円滑化法がH25年3月で終了することに伴って、金融機関は返済猶予の継続に応じない企業に対しては、当初の返済額での返済を要求し返済不能となれば、期限の利益喪失によって、保証協会の代位弁済やサービサー等への債権売却へと進むことになるでしょう。」と、書きました。
通常、金融機関との約定の弁済がなされず期限の利益が喪失となってから、90日(一部の協会は60日)を経過すると、金融機関は保証協会に対して代位弁済の請求ができます。
保証協会が金融機関に対して代位弁済すると、保証協会が債務者に対して求償権を取得することになります。ですから、代位弁済以後は、返済の交渉相手が金融機関から保証協会に変わるということです。
事態がここまで進んだ場合、企業としては新たな借り入れは困難になりますが、担保不動産の処分等を通じて返済できる分は返済し、残った債務をコツコツと返すことによって再起を図ることができるという考え方もあります。
この場合、商品仕入や外注費や給料などは、すべて自己資金で決済することになりますので、手元資金の確保が絶対に必要になりますから、さまざまな困難がついてまわることが予想されますが、「期限の利益喪失」や「代位弁済」が、即、倒産につながるわけではないことだけは必ず経営者として理解しておきましょう。
特に、リ・スケジュールで資金繰りが出来ていた企業は、代位弁済後も状況的には、さほど変わらないはずです。担保不動産の処分その他出来る限りの弁済について、誠意をもって保証協会に対応すれば、協会が強硬なことを言い出す可能性は低いですから、落ち着いて対応することが肝要です。
なお、【倒産を回避して再起を図るなら、担保不動産の処分は競売は回避し可能な限り高値で出来るようにするべきです。】←これは大きなポイントです。
事業再生には、法律、金融取引、不動産流通、税金の知識が不可欠です。偏った知識で対応すると結果的に損をすることや挫折することも多々あります。ぜひ、専門家にご相談ください。
Posted by 開設者 at 10:27│Comments(0)
│事業再生
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。