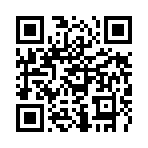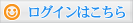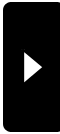大人のケンカ術
2010年02月11日
今日、読んだ本。大人のケンカ術
著者は、現在テレビドラマになっている「特上カバチ」の原作者、田島隆氏です。氏は現役の海事代理士、行政書士です。この本で、氏の苦労された半生を知りました。それが、漫画に現れていたのだと思いました。現役の自営業者でありながら、漫画のテーマの取材からストーリーの構成に至るまでの作業は大変な努力が要るだろうなと、いつも思っています。
この本で、私も忘れかけていたスピリッツを思い出させてもらいました。私が法律に出会ったのは大学を卒業してからです。法学部でもない大学を卒業したので当然ですが。ときに法が人を救い、ときに法が人を痛めつける。そういう明暗の部分を持つ法の世界。田島氏の本に深く共感するものがあります。
ただ、けれども少し違和感があるのが、「結局、法律というのはただの屁理屈なんだ」と感じるというくだりです。カバチタレというのが広島地方の方言で、まさに屁理屈なのだそうですが、地方によって感覚がかなり違うのかもしれませんけれども、私など「屁理屈」というものには邪なイメージを強く持ちます。
邪なイメージがあるというのは、子供の頃、大人に文句を言うと「子供のくせに屁理屈を言うな!」などと叱られた記憶が強く残っているからかもしれません。確かに大人は大人の論理で子供を制圧しようとして、子供の論理を否定するのに、「屁理屈」という一語で一蹴しようとしたのかもしれません。そういう意味で「屁理屈」というのは常識人を気取る大人にとって非常に便利な言葉ですね。
そう言いながらも、「結局、法律というのはただの屁理屈なんだ」ということに、なぜ私が違和感を感じるのか。それは、大勢が暮らす人間社会にあって法がなくてはならないものだからです。スポーツにルールが必要なのと同じように社会には法というルールが必要だと感ずるからなのです。
事実、変な法もあります。特定の人が利益を得るために存在するかのような法も確かにあります。しかし、すべてがそうではなくて、なくてはならない法もあるのです。それを一括りにしてすべて屁理屈というのは言い過ぎでしょう。人がみんな歩いていた時代、せいぜい走るか馬に乗るくらいの時代なら道路交通法は要らないかもしれませんが、自動車の時代になれば道路交通法はなくてはならない法です。
大事なことは、法を知ることでしょう。法によって円滑な社会生活を営むことは、ルールを知ってスポーツを楽しむのと同じです。ルールを知らずに上達できるスポーツが無いように、法というルールを知らずに円滑な社会生活を営むことは難しいように思います。だから、すべての法を屁理屈と片付けることには賛成しかねるのです。
屁理屈でない法、それは、大多数が納得できる法です。だから民主主義の国では、選挙で選ばれた議員が法を作ることになっているのですね。法の成立過程から施行、運用まで、多くの人が納得できる法こそが望まれるでしょう。ゆえに一部の特権階級に世の中が支配されるようなことのないように市民がこれらを監視する必要があります。
著者は、現在テレビドラマになっている「特上カバチ」の原作者、田島隆氏です。氏は現役の海事代理士、行政書士です。この本で、氏の苦労された半生を知りました。それが、漫画に現れていたのだと思いました。現役の自営業者でありながら、漫画のテーマの取材からストーリーの構成に至るまでの作業は大変な努力が要るだろうなと、いつも思っています。
この本で、私も忘れかけていたスピリッツを思い出させてもらいました。私が法律に出会ったのは大学を卒業してからです。法学部でもない大学を卒業したので当然ですが。ときに法が人を救い、ときに法が人を痛めつける。そういう明暗の部分を持つ法の世界。田島氏の本に深く共感するものがあります。
ただ、けれども少し違和感があるのが、「結局、法律というのはただの屁理屈なんだ」と感じるというくだりです。カバチタレというのが広島地方の方言で、まさに屁理屈なのだそうですが、地方によって感覚がかなり違うのかもしれませんけれども、私など「屁理屈」というものには邪なイメージを強く持ちます。
邪なイメージがあるというのは、子供の頃、大人に文句を言うと「子供のくせに屁理屈を言うな!」などと叱られた記憶が強く残っているからかもしれません。確かに大人は大人の論理で子供を制圧しようとして、子供の論理を否定するのに、「屁理屈」という一語で一蹴しようとしたのかもしれません。そういう意味で「屁理屈」というのは常識人を気取る大人にとって非常に便利な言葉ですね。
そう言いながらも、「結局、法律というのはただの屁理屈なんだ」ということに、なぜ私が違和感を感じるのか。それは、大勢が暮らす人間社会にあって法がなくてはならないものだからです。スポーツにルールが必要なのと同じように社会には法というルールが必要だと感ずるからなのです。
事実、変な法もあります。特定の人が利益を得るために存在するかのような法も確かにあります。しかし、すべてがそうではなくて、なくてはならない法もあるのです。それを一括りにしてすべて屁理屈というのは言い過ぎでしょう。人がみんな歩いていた時代、せいぜい走るか馬に乗るくらいの時代なら道路交通法は要らないかもしれませんが、自動車の時代になれば道路交通法はなくてはならない法です。
大事なことは、法を知ることでしょう。法によって円滑な社会生活を営むことは、ルールを知ってスポーツを楽しむのと同じです。ルールを知らずに上達できるスポーツが無いように、法というルールを知らずに円滑な社会生活を営むことは難しいように思います。だから、すべての法を屁理屈と片付けることには賛成しかねるのです。
屁理屈でない法、それは、大多数が納得できる法です。だから民主主義の国では、選挙で選ばれた議員が法を作ることになっているのですね。法の成立過程から施行、運用まで、多くの人が納得できる法こそが望まれるでしょう。ゆえに一部の特権階級に世の中が支配されるようなことのないように市民がこれらを監視する必要があります。
Posted by 開設者 at 22:37│Comments(0)
│業務案内
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。