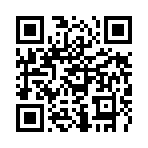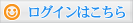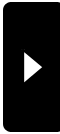明るい貧乏人
2009年11月22日
我が家で購読しています京都新聞の11月19日夕刊に桂都丸さんという落語家さんが「明るい貧乏人」というタイトルでコラムを書いておられました。桂都丸さんをネットで調べると昭和30年生まれとありましたので私より4つ年上です。それで、そのコラムに書かれていた都丸さんの子供時分の話は私の子供時分にあったことが、そのままだったので懐かしく読んだのです。
都丸さんは京都の壬生で生まれ育ったとあります。私はそこより東南に5キロくらいの伏見区深草というところで生まれ育ったので、場所的にも近いものがあります。昭和30年代といえば戦争の痕は無くなりつつありましたが、全国的に有名な伏見稲荷大社へ参詣する人がたくさん歩く道には傷痍軍人さんが居ました記憶があります。
さて都丸さんの書かれた明るい貧乏人ですが、当時は高度成長前で下町で暮らす人々の多くが裕福ではなかったが、近所の結びつきが強く、おかずの貸し借り、もらい湯などが当たり前の世の中だったとあります。確かにそんな雰囲気がありました。特に「電話の呼び出し」の記述があり懐かしさが込み上げてきました。
電話の呼び出しとは、携帯電話が普及した今の子供たちには信じられないでしょうが当時、電話のある家は多くなく、用事のある人から近所の電話のある家に電話を架けてもらって、そこの人が電話のない家の人を呼びに行くというものです。
コラムを読んで、私の母方の実家には電話がなく近くの酒屋さんか風呂屋さんに頼んでいたことを思い出しました。何とのんびりした時代だったのかと改めて思います。そのかわり携帯電話代を払うこともなかったわけですから貧乏でも生きていけたのです。
ところが今はそういう訳には行きません。呼び出し電話を頼むことなど恥ずかしくて出来ないし、たいてい携帯電話を持っています。便利になったわけですが、便利の代償として決して安くない携帯電話代を稼ぐ必要に迫られます。コラムにもありますが、先日、厚労省から発表された日本の貧困率は15.7%だそうです。
勝ち組負け組という言われ方が象徴するように優勝劣敗のシステムで経済成長を追及した結果が大変な格差を生んだとも言えるでしょう。また豊かになって財を持てば物やサービスが手に入れられるということで個人主義的な風潮が強まり隣近所で食べ物を貸し借りするようなこともない代わりに、財を持たないとニッチもサッチも行かない世の中なのです。
都丸さんもコラムに書かれていますが、まさか昔のような明るい貧乏な時代に戻ることも無理でしょうが、でも、「日本人が大切にしてきた「お互い様」の気持ち、人との「和」、そこに生まれるコミュニケーションを考え直すことはできる」と思います。
鳩山首相は新政権発足にあたり友愛の社会づくりを謳っています。より良いサービスや商品を得るためには必要な競争もあるでしょうが、競争だけで発展しようとする社会から明確に転換する必要があるように私は思います。
都丸さんは京都の壬生で生まれ育ったとあります。私はそこより東南に5キロくらいの伏見区深草というところで生まれ育ったので、場所的にも近いものがあります。昭和30年代といえば戦争の痕は無くなりつつありましたが、全国的に有名な伏見稲荷大社へ参詣する人がたくさん歩く道には傷痍軍人さんが居ました記憶があります。
さて都丸さんの書かれた明るい貧乏人ですが、当時は高度成長前で下町で暮らす人々の多くが裕福ではなかったが、近所の結びつきが強く、おかずの貸し借り、もらい湯などが当たり前の世の中だったとあります。確かにそんな雰囲気がありました。特に「電話の呼び出し」の記述があり懐かしさが込み上げてきました。
電話の呼び出しとは、携帯電話が普及した今の子供たちには信じられないでしょうが当時、電話のある家は多くなく、用事のある人から近所の電話のある家に電話を架けてもらって、そこの人が電話のない家の人を呼びに行くというものです。
コラムを読んで、私の母方の実家には電話がなく近くの酒屋さんか風呂屋さんに頼んでいたことを思い出しました。何とのんびりした時代だったのかと改めて思います。そのかわり携帯電話代を払うこともなかったわけですから貧乏でも生きていけたのです。
ところが今はそういう訳には行きません。呼び出し電話を頼むことなど恥ずかしくて出来ないし、たいてい携帯電話を持っています。便利になったわけですが、便利の代償として決して安くない携帯電話代を稼ぐ必要に迫られます。コラムにもありますが、先日、厚労省から発表された日本の貧困率は15.7%だそうです。
勝ち組負け組という言われ方が象徴するように優勝劣敗のシステムで経済成長を追及した結果が大変な格差を生んだとも言えるでしょう。また豊かになって財を持てば物やサービスが手に入れられるということで個人主義的な風潮が強まり隣近所で食べ物を貸し借りするようなこともない代わりに、財を持たないとニッチもサッチも行かない世の中なのです。
都丸さんもコラムに書かれていますが、まさか昔のような明るい貧乏な時代に戻ることも無理でしょうが、でも、「日本人が大切にしてきた「お互い様」の気持ち、人との「和」、そこに生まれるコミュニケーションを考え直すことはできる」と思います。
鳩山首相は新政権発足にあたり友愛の社会づくりを謳っています。より良いサービスや商品を得るためには必要な競争もあるでしょうが、競争だけで発展しようとする社会から明確に転換する必要があるように私は思います。
遺産分割の話し合いが着く前でも預金の一部の引き出しが可能に
年の初めの会社設立
滋賀県行政書士会湖南支部の無料相談会
親族間不動産売買の住宅ローン
ご依頼者様から嬉しい「お客様の声」を頂きました!(任意売却)
大雪の中、住宅の任意売却の取引が1件、無事完了
年の初めの会社設立
滋賀県行政書士会湖南支部の無料相談会
親族間不動産売買の住宅ローン
ご依頼者様から嬉しい「お客様の声」を頂きました!(任意売却)
大雪の中、住宅の任意売却の取引が1件、無事完了
Posted by 開設者 at 13:03│Comments(0)
│もろもろ
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。