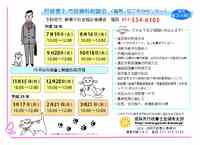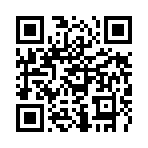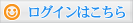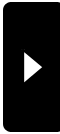遺産分割の話し合いが着く前でも預金の一部の引き出しが可能に
2019年01月09日
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO38936780U8A211C1000000?type=my&fbclid=IwAR12CoaQeHep3M1yGDDhDCATydsBjHe4039UDn4HrWoAqlnqe5-YLbhm2Tg
預貯金の遺産分割前の払戻し制度が創設されます。
人が亡くなると、その人の預貯金の口座が凍結(ロック)されて引き出しが出来なくなるということは、一般に知られることになっていました。ですんで、亡くなる前におろしておけとか。
でも、この直前の引き出しや凍結がもとで、相続の紛争に発展したり、金融機関ともめたりといった混乱もありました。
そもそも金融機関との、もめ事の元凶は、「預貯金は相続開始と同時に分割されているもんね。だから、その分は一人で払い戻してもらえるよ。」という裁判所の判断にあったわけですが、
でも、金融機関としては、「そんなことして相続人の一人に払い戻したら他の相続人からクレームがついて二重払いさせられたらいやだもんね。」と拒否されることが普通でした。
ところが、平成28年に、裁判所の判断が変わって、「やっぱり皆のハンコが揃わないとあかんわ。」ということに成ってしまいました。
それでは、葬儀費用の支払いに、はたまた、亡くなった人に養われていた人がたちまち生活費がなくて、困るということで、裁判所を通さない簡易な方法として、次のような預貯金の一部の払い戻し制度が創設されます。
『各共同相続人は、遺産の預貯金債権のうち、各口座ごとに以下の計算式による額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、150万円が限度。)までについては、他の相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができる。』
【計算式】
単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める相続人の法定相続分)
結局、初めの記事にある、例えで言えば
相続人が長男と次男の2人の場合で、両者の法定相続分は2分の1で、遺産が預金のみ(1つの金融機関で1口座のみ)1000万円だとすると各人のその相続分は500万円。
その3分の1は約166万円ですが、1つの金融機関に対しては150万が限度となってますから、この場合、相続人の一人につき150万が払い戻しを受けられる限度額になります。
なお、この制度は2019年7月1日から始まりますが、それ以前に開始した相続についても、2019年7月1日以後に金融機関に払い戻し請求する場合は適用されます。
ただ、特にこの制度の開始当初は金融機関の窓口の対応は慎重で時間がかかりそうですが、はたしてどうなるでしょうか。
預貯金の遺産分割前の払戻し制度が創設されます。
人が亡くなると、その人の預貯金の口座が凍結(ロック)されて引き出しが出来なくなるということは、一般に知られることになっていました。ですんで、亡くなる前におろしておけとか。
でも、この直前の引き出しや凍結がもとで、相続の紛争に発展したり、金融機関ともめたりといった混乱もありました。
そもそも金融機関との、もめ事の元凶は、「預貯金は相続開始と同時に分割されているもんね。だから、その分は一人で払い戻してもらえるよ。」という裁判所の判断にあったわけですが、
でも、金融機関としては、「そんなことして相続人の一人に払い戻したら他の相続人からクレームがついて二重払いさせられたらいやだもんね。」と拒否されることが普通でした。
ところが、平成28年に、裁判所の判断が変わって、「やっぱり皆のハンコが揃わないとあかんわ。」ということに成ってしまいました。
それでは、葬儀費用の支払いに、はたまた、亡くなった人に養われていた人がたちまち生活費がなくて、困るということで、裁判所を通さない簡易な方法として、次のような預貯金の一部の払い戻し制度が創設されます。
『各共同相続人は、遺産の預貯金債権のうち、各口座ごとに以下の計算式による額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、150万円が限度。)までについては、他の相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができる。』
【計算式】
単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める相続人の法定相続分)
結局、初めの記事にある、例えで言えば
相続人が長男と次男の2人の場合で、両者の法定相続分は2分の1で、遺産が預金のみ(1つの金融機関で1口座のみ)1000万円だとすると各人のその相続分は500万円。
その3分の1は約166万円ですが、1つの金融機関に対しては150万が限度となってますから、この場合、相続人の一人につき150万が払い戻しを受けられる限度額になります。
なお、この制度は2019年7月1日から始まりますが、それ以前に開始した相続についても、2019年7月1日以後に金融機関に払い戻し請求する場合は適用されます。
ただ、特にこの制度の開始当初は金融機関の窓口の対応は慎重で時間がかかりそうですが、はたしてどうなるでしょうか。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。