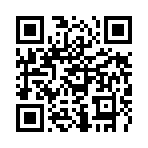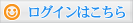遺言と遺書は違います
2013年12月25日
昨日、紛争の火種になることが多い法定相続よりも、遺言による相続が増えたほうが良いという趣旨のことを書きました。
その中で、「遺言というと何だか縁起が悪いとか、死ぬのを待たれているようだとかいうような考えに囚われてタブーのように思われる人」もあると書いたのですが、その原因について、いろいろ考えた中で、
どうも、一般に遺言と遺書が混同されたり、あるいはイメージとしてダブってしまっているのではないかという思いが大きくなりました。
次は、ウィキペディアの「遺言」の冒頭の引用です。
『遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。このうち民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。法律用語としてはいごんと読まれることが多い。』
次が、ウィキペディアの「遺書」の冒頭の引用です。
『遺書(いしょ)は自殺する人、又は死ぬことが確実な人が残す文章である。』
しかも、遺書のページには、「財産分与などの法律的な問題を記す「遺言書」とは異なります。」と、わざわざ書いてあります。
これは、一般に遺言と遺書が混同されたり、あるいはイメージとしてダブってしまっている怖れがあるから、わざわざ書いてあるのでしょう。
遺言の上記説明のなかにもあるように、遺言も遺書も「広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章」と、とらえると同じであり、この二つを混同されるのも無理はないと思います。
そして、その結果、遺言も遺書と同じく自殺する人、又は死ぬことが確実な人が書くものと誤解されたら、そりゃ、遺言も忌み嫌われるべきものというイメージになってしまいますよね。
でも、遺書のページに注意書きされているように、遺書と財産分与などの法律的な問題を記す遺言「書」とは根本的に違います。
自分の財産を自分が使えなくなったとき(死後)、その財産をどのようにして欲しいかという意思(又は遺志)を法律的に有効なものとして表すのが遺言です。
それは、誰か好きな人に何かプレゼントする、ご先祖から承継してきたものを特定の人に託すといった、財産上の法的処分行為です。(遺言でなしうることは、このほかにもありますが、ここでは割愛します。)
相続の法定事項は、被相続人の意思によって修正することができる、そこには民事法の原則である私的自治の考え方があらわれているのです。
被相続人にとって遺す財産は、すなわち相続人が受け取る財産です。
相続は私が死んだあとのことで、相続人が考えることとか、法律で決まっていることと思っている人がいるかもしれません。
でも、「後は野となれ山となれ、私の死んだあとのことは知ったことじゃない。」と、本当に考えている人は、どちらかと言えば少ないのではないでしょうか。
被相続人と関係の深い相続人が困るようなことがないように配慮すべきはマナーであり、思いやりであるというような意識が一般に広まることを期待したいものです。
そのために、遺言なき相続が、実はやっかいなものであるということと、一方で、問題のある遺言によって、かえってトラブルが起こることもあることをも併せて、理解してもらうために私も情報発信していきたいと考えています。
その中で、「遺言というと何だか縁起が悪いとか、死ぬのを待たれているようだとかいうような考えに囚われてタブーのように思われる人」もあると書いたのですが、その原因について、いろいろ考えた中で、
どうも、一般に遺言と遺書が混同されたり、あるいはイメージとしてダブってしまっているのではないかという思いが大きくなりました。
次は、ウィキペディアの「遺言」の冒頭の引用です。
『遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。このうち民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。法律用語としてはいごんと読まれることが多い。』
次が、ウィキペディアの「遺書」の冒頭の引用です。
『遺書(いしょ)は自殺する人、又は死ぬことが確実な人が残す文章である。』
しかも、遺書のページには、「財産分与などの法律的な問題を記す「遺言書」とは異なります。」と、わざわざ書いてあります。
これは、一般に遺言と遺書が混同されたり、あるいはイメージとしてダブってしまっている怖れがあるから、わざわざ書いてあるのでしょう。
遺言の上記説明のなかにもあるように、遺言も遺書も「広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章」と、とらえると同じであり、この二つを混同されるのも無理はないと思います。
そして、その結果、遺言も遺書と同じく自殺する人、又は死ぬことが確実な人が書くものと誤解されたら、そりゃ、遺言も忌み嫌われるべきものというイメージになってしまいますよね。
でも、遺書のページに注意書きされているように、遺書と財産分与などの法律的な問題を記す遺言「書」とは根本的に違います。
自分の財産を自分が使えなくなったとき(死後)、その財産をどのようにして欲しいかという意思(又は遺志)を法律的に有効なものとして表すのが遺言です。
それは、誰か好きな人に何かプレゼントする、ご先祖から承継してきたものを特定の人に託すといった、財産上の法的処分行為です。(遺言でなしうることは、このほかにもありますが、ここでは割愛します。)
相続の法定事項は、被相続人の意思によって修正することができる、そこには民事法の原則である私的自治の考え方があらわれているのです。
被相続人にとって遺す財産は、すなわち相続人が受け取る財産です。
相続は私が死んだあとのことで、相続人が考えることとか、法律で決まっていることと思っている人がいるかもしれません。
でも、「後は野となれ山となれ、私の死んだあとのことは知ったことじゃない。」と、本当に考えている人は、どちらかと言えば少ないのではないでしょうか。
被相続人と関係の深い相続人が困るようなことがないように配慮すべきはマナーであり、思いやりであるというような意識が一般に広まることを期待したいものです。
そのために、遺言なき相続が、実はやっかいなものであるということと、一方で、問題のある遺言によって、かえってトラブルが起こることもあることをも併せて、理解してもらうために私も情報発信していきたいと考えています。