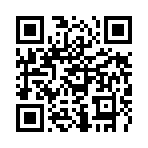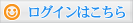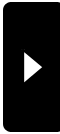いきなり破産は回避したい
2012年07月22日
昨日、倒産に関して、何らの準備もなしにいきなり自己破産してしまう社長が多いと書きましたが、今日は、ここでいう準備ってどういうことかについて、書いてみます。
理解していただき易いように、まず、はじめに、破産のメリット・デメリットの説明からします。
破産(免責の許可)の最大のメリットは、「特定の債務」以外の全ての債務から解放されることです。(正確には破産宣告を受けただけでは債務から解放されず免責の許可を受けることが必要です。破産宣告は債務者が破産状態にあることの確認を受けただけのようなものです。)
ここでいう、「特定の債務」とは、被免責債権と呼ばれる債権に対応する債務です。破産者が、故意や重過失で加えた人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権などが、その例です。
とにかく、普通の債務は全て帳消しです。返済しきれない債務を破産・免責制度を使って整理することは、債務奴隷からの解放であり、再起の機会を得るものですし、生活保護制度などと同様に、濫用の危険はあるものの、社会のセーフティネットとして重要な制度であることは間違いありません。
一方、破産のデメリットとして、一般に言われているのは、クレジットカードが持てない、ローンが組めない、一定の職業に就けない(免責の許可が出れば問題ないです。)などですが、ぜんぜん大したことはありませんなんて説明しているサイトなどもありますが、これは、概ね個人の、いわゆる消費者破産に当てはまるものです。
では、事業者の破産はどうなるの?会社は破産手続きの終結と同時に消滅します。つまり、会社の臨終です。
さて、会社はそれで終わりました。でも、元社長は生活して行かなければなりません。その生活の糧は、どうなりますか?
元社長に特殊な能力・技能があるとかすれば、すぐに裸一つで出直せるかもしれませんが、そういう方は、そう多くないようです。
昨日も書きましたが、小規模零細事業者の事業の資本である重要な資源は、大規模な建物や機械などのハード資源よりも、知識、経験、ノウハウ、人財、信用、取引先との関係などのソフト資源である場合が多いでしょう。
まず、早期の出直しには、ソフト資源が必要なのではないでしょうか?知識、経験、ノウハウ、人財、信用、取引先との関係などは、普通、目に見えませんが、相互に関係し合って威力を発揮するものです。
が、しかし、いきなり自己破産の場合は、これらをズタズタにしてしまいます。人財は解雇で、材料・商品の購入先や外注先との関係は不払いで、受注先との関係は商品・サービスの提供不能で、それぞれが空中分解して無くなります。
では、破産手続きの中で、せめて、これらの資源を壊さないことができないかと模索しても、まず、無理でしょう。特に、材料購入先や外注先との関係は不払いで最大の迷惑をかけます。迷惑を受けたほうは恨みます。下手すれば連鎖的な危機に直面します。これが、再起の大きなネックになります。つまり、再起についての協力者が居ない状況になってしまうのです。
だからといって、これらの人に迷惑をかけないように、支払いをすることは破産手続きの中ではできません。債権者平等の原則というものがあるからです。
でも、この債権者平等の原則も実は真の意味では平等ではありません。通常、金融機関は不動産担保を持っています。不動産担保は別除権といって、破産手続きとは関係なく売却して代金から回収することができるのです。小規模零細企業は不動産がない場合も多いですが、その場合は信用保証協会の保証があることが多く、金融機関はここでも別途回収が可能なのです。
だから、実質、迷惑をかけるのは焦げ付きを持たされた取引先や職を失った人財です。そして、元社長は再起が遠のきます。ゆえに、後のことを考えずに、いきなり自己破産することは、デメリットが大きいと言えるのです。
さて、いきなり自己破産ではなく、準備をという話に戻りますが、ここまで説明すると、だいたいお分かり頂けると思います。危機的状況下でもソフト資源を温存し、場合によっては事業だけでも残せるようにすることが大切です。つまり、事業と会社の切り分けですね。
そうした準備のうえで、自己破産のメリットを享受することは良いかもしれませんが、いきなり法的手続きに入ったのでは、準備も何も出来ません。
でも、いきなり、法律(弁護士)事務所に相談に行くと、いきなり、自己破産になりがちですよ!
理解していただき易いように、まず、はじめに、破産のメリット・デメリットの説明からします。
破産(免責の許可)の最大のメリットは、「特定の債務」以外の全ての債務から解放されることです。(正確には破産宣告を受けただけでは債務から解放されず免責の許可を受けることが必要です。破産宣告は債務者が破産状態にあることの確認を受けただけのようなものです。)
ここでいう、「特定の債務」とは、被免責債権と呼ばれる債権に対応する債務です。破産者が、故意や重過失で加えた人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権などが、その例です。
とにかく、普通の債務は全て帳消しです。返済しきれない債務を破産・免責制度を使って整理することは、債務奴隷からの解放であり、再起の機会を得るものですし、生活保護制度などと同様に、濫用の危険はあるものの、社会のセーフティネットとして重要な制度であることは間違いありません。
一方、破産のデメリットとして、一般に言われているのは、クレジットカードが持てない、ローンが組めない、一定の職業に就けない(免責の許可が出れば問題ないです。)などですが、ぜんぜん大したことはありませんなんて説明しているサイトなどもありますが、これは、概ね個人の、いわゆる消費者破産に当てはまるものです。
では、事業者の破産はどうなるの?会社は破産手続きの終結と同時に消滅します。つまり、会社の臨終です。
さて、会社はそれで終わりました。でも、元社長は生活して行かなければなりません。その生活の糧は、どうなりますか?
元社長に特殊な能力・技能があるとかすれば、すぐに裸一つで出直せるかもしれませんが、そういう方は、そう多くないようです。
昨日も書きましたが、小規模零細事業者の事業の資本である重要な資源は、大規模な建物や機械などのハード資源よりも、知識、経験、ノウハウ、人財、信用、取引先との関係などのソフト資源である場合が多いでしょう。
まず、早期の出直しには、ソフト資源が必要なのではないでしょうか?知識、経験、ノウハウ、人財、信用、取引先との関係などは、普通、目に見えませんが、相互に関係し合って威力を発揮するものです。
が、しかし、いきなり自己破産の場合は、これらをズタズタにしてしまいます。人財は解雇で、材料・商品の購入先や外注先との関係は不払いで、受注先との関係は商品・サービスの提供不能で、それぞれが空中分解して無くなります。
では、破産手続きの中で、せめて、これらの資源を壊さないことができないかと模索しても、まず、無理でしょう。特に、材料購入先や外注先との関係は不払いで最大の迷惑をかけます。迷惑を受けたほうは恨みます。下手すれば連鎖的な危機に直面します。これが、再起の大きなネックになります。つまり、再起についての協力者が居ない状況になってしまうのです。
だからといって、これらの人に迷惑をかけないように、支払いをすることは破産手続きの中ではできません。債権者平等の原則というものがあるからです。
でも、この債権者平等の原則も実は真の意味では平等ではありません。通常、金融機関は不動産担保を持っています。不動産担保は別除権といって、破産手続きとは関係なく売却して代金から回収することができるのです。小規模零細企業は不動産がない場合も多いですが、その場合は信用保証協会の保証があることが多く、金融機関はここでも別途回収が可能なのです。
だから、実質、迷惑をかけるのは焦げ付きを持たされた取引先や職を失った人財です。そして、元社長は再起が遠のきます。ゆえに、後のことを考えずに、いきなり自己破産することは、デメリットが大きいと言えるのです。
さて、いきなり自己破産ではなく、準備をという話に戻りますが、ここまで説明すると、だいたいお分かり頂けると思います。危機的状況下でもソフト資源を温存し、場合によっては事業だけでも残せるようにすることが大切です。つまり、事業と会社の切り分けですね。
そうした準備のうえで、自己破産のメリットを享受することは良いかもしれませんが、いきなり法的手続きに入ったのでは、準備も何も出来ません。
でも、いきなり、法律(弁護士)事務所に相談に行くと、いきなり、自己破産になりがちですよ!
社長、倒産を誤解してませんか?
2012年07月21日
世に俗説の多いのが、「倒産」に関するものです。さて、倒産とは何でしょう?
1 債務不履行→支払いや弁済の約束が守れなくなった状態
2 手形の不渡り→銀行取引停止
3 訴訟を提起された(敗訴のうえ支払えとの判決を受けた)
4 差し押さえを受けた
5 不動産等の競売を申し立てられた
上記全ては事業の危機ではありますが、倒産ではありません。
しかし、上記いずれの状態になっても(或いは複数の状態であっても)、粘り強く、持ち堪えて、事業を継続しておられるケースは、たくさん、あります。
じゃ、倒産って何?
倒産の典型は、破産です。しかも、世の中の破産の大多数は自己破産です。破産は債権者も債務者も申し立てできますが、債権者が申し立てすることは稀です。
何故か?破産の申し立てをせざるを得ない状況の債務者に、無傷で残る財産が殆どないのが普通だからです。
債権者からしたら、破産してもらっても回収できるものがないなら、なんとか事業を継続してもらって、少しでも回収したいというのが本音です。
(ただし、債権者から見て、債務者の破産にメリットが全くないかといえば、そんなことはありません。儲かっている債権者は本来払うべき税金で何割かは回収したのと同じ状態になることもあり、不良債権の管理コストの削減につながることもあるからです。)
零細企業の倒産は、ほとんど自己破産か、夜逃げなどの自主的な事業停止です。前者には弁護士や管財人の費用が要ります。費用が捻出できない場合は後者になることが多いようです。
ですから、逆から言うと、社長の心が折れて上の二つのいずれかを選択しない限り、企業は簡単に潰れないのです。
小規模零細事業者の事業の資本である重要な資源は、大規模な建物や機械などのハード資源よりも、知識、経験、ノウハウ、人財、信用、取引先との関係などのソフト資源である場合が多いでしょう。
ハード資源は換価ができますから、いざとなったら持って行かれる可能性はありますが、ソフト資源は普通、持って行きようがありません。だから、元から取られる心配はないのです。
でも、破産や夜逃げを選択すると、ソフト資源が空中分解し、通常、すべて(社長の身に付いているものを除き。)、無くなります。
であるにも関わらず、何らの準備もなしに、いきなり破産や夜逃げを選択する社長が後を絶ちません。何故でしょう?
恐怖、不安が先に立ち、冷静な判断能力を失い、とりあえず、目の前の苦しみから逃れたいからではないでしょうか?
根本は、倒産というものについて、余りにも無知だからだと私は思います。でも、それは無理もありません。そんなことは学校で習いませんし、事業をするに際しても、前を向いて一生懸命頑張るのに忙しくて、後ろ向きな事業の危機対策なんて、普通の社長は考えませんから。
倒産回避を検討する場合に、下の3つが、まず、するべきことです。
1 倒産というものを正確に知る。
2 自分のビジネスモデルが、本来、利益を出せるものかどうか落ち着いて考える。
3 2の結果、利益を出せるものだとしたら、次に打つ手を考える。
利益が出せるビジネスモデルであれば、事業の再生はできるはずです。
1 債務不履行→支払いや弁済の約束が守れなくなった状態
2 手形の不渡り→銀行取引停止
3 訴訟を提起された(敗訴のうえ支払えとの判決を受けた)
4 差し押さえを受けた
5 不動産等の競売を申し立てられた
上記全ては事業の危機ではありますが、倒産ではありません。
しかし、上記いずれの状態になっても(或いは複数の状態であっても)、粘り強く、持ち堪えて、事業を継続しておられるケースは、たくさん、あります。
じゃ、倒産って何?
倒産の典型は、破産です。しかも、世の中の破産の大多数は自己破産です。破産は債権者も債務者も申し立てできますが、債権者が申し立てすることは稀です。
何故か?破産の申し立てをせざるを得ない状況の債務者に、無傷で残る財産が殆どないのが普通だからです。
債権者からしたら、破産してもらっても回収できるものがないなら、なんとか事業を継続してもらって、少しでも回収したいというのが本音です。
(ただし、債権者から見て、債務者の破産にメリットが全くないかといえば、そんなことはありません。儲かっている債権者は本来払うべき税金で何割かは回収したのと同じ状態になることもあり、不良債権の管理コストの削減につながることもあるからです。)
零細企業の倒産は、ほとんど自己破産か、夜逃げなどの自主的な事業停止です。前者には弁護士や管財人の費用が要ります。費用が捻出できない場合は後者になることが多いようです。
ですから、逆から言うと、社長の心が折れて上の二つのいずれかを選択しない限り、企業は簡単に潰れないのです。
小規模零細事業者の事業の資本である重要な資源は、大規模な建物や機械などのハード資源よりも、知識、経験、ノウハウ、人財、信用、取引先との関係などのソフト資源である場合が多いでしょう。
ハード資源は換価ができますから、いざとなったら持って行かれる可能性はありますが、ソフト資源は普通、持って行きようがありません。だから、元から取られる心配はないのです。
でも、破産や夜逃げを選択すると、ソフト資源が空中分解し、通常、すべて(社長の身に付いているものを除き。)、無くなります。
であるにも関わらず、何らの準備もなしに、いきなり破産や夜逃げを選択する社長が後を絶ちません。何故でしょう?
恐怖、不安が先に立ち、冷静な判断能力を失い、とりあえず、目の前の苦しみから逃れたいからではないでしょうか?
根本は、倒産というものについて、余りにも無知だからだと私は思います。でも、それは無理もありません。そんなことは学校で習いませんし、事業をするに際しても、前を向いて一生懸命頑張るのに忙しくて、後ろ向きな事業の危機対策なんて、普通の社長は考えませんから。
倒産回避を検討する場合に、下の3つが、まず、するべきことです。
1 倒産というものを正確に知る。
2 自分のビジネスモデルが、本来、利益を出せるものかどうか落ち着いて考える。
3 2の結果、利益を出せるものだとしたら、次に打つ手を考える。
利益が出せるビジネスモデルであれば、事業の再生はできるはずです。
倒産寸前からの復活
2012年07月20日
今回は信用保証協会の制度のうちで求償権消滅保証制度をご紹介します。この制度は倒産寸前の危機に陥った小規模企業が瀬戸際からの復活を果たすのに有効なものです。
一時的に業況が悪化したことなどから借入金元本返済が困難となり、保証協会が金融機関に代位弁済をしたケースでは、当該事業者がその後も事業を継続する場合に、金融機関との取引は事故扱いとなっていることから、新たな資金調達に支障をきたすなどの問題が発生します。
そのような事業者に対しては、保証協会がその求償権を借換えるための保証を行うことは原則として禁止されていましたが、平成18 年4 月からは、その事業者に自力再生の見込みがあり、今後の事業計画や債務弁済計画を含めた経営改善計画を策定し、その計画が外部の専門家や有識者で組織された再生審査会で承認された場合に、その求償権を借換えるための保証である求償権消滅保証を行うことができるようになりました。
簡単に言いますと、金融機関との約定弁済(毎月の返済)ができなくなり、保証協会が金融機関に肩代わりで弁済した場合でも、一定の条件のもとで、もとの正常な金融取引の状態に戻してあげようということです。
保証協会は国の制度であり、中小企業の支援を目的としていることから、金融機関より融通の利くことも多く、代位弁済になったからといって、全てを投げ出す必要はないということですね。
さて、一定の条件とは一律決まっているわけではありませんが、下記のような取り組みは最低限必要でしょう。
1 できるだけ可能で誠実な義務(返済や資料提出等)の履行
2 事業の見直しの中で、可能な限りのコストカット
3 不要な資産の売却による負債の縮小
4 黒字体質の構築
事業の見直しについては、過去の売り上げ重視の戦略から利益重視へ、事業の選択と資源の集中投下、一貫性のある成長戦略の構築が求められます。これらを具体的かつ見える化した経営改善計画の策定が必要となるでしょう。
私どもでは、一口に事業再生支援と言っても、小規模零細事業者の場合は、「事業再生支援」と言うより「経営改善への支援」と言ったスタンスで取り組むほうが妥当ではないかと考え、「危機に至った原因が何だったのか」また、「経営改善のためのポイントは何か」などを経営者と一緒に考える取り組みを致しております。
一時的に業況が悪化したことなどから借入金元本返済が困難となり、保証協会が金融機関に代位弁済をしたケースでは、当該事業者がその後も事業を継続する場合に、金融機関との取引は事故扱いとなっていることから、新たな資金調達に支障をきたすなどの問題が発生します。
そのような事業者に対しては、保証協会がその求償権を借換えるための保証を行うことは原則として禁止されていましたが、平成18 年4 月からは、その事業者に自力再生の見込みがあり、今後の事業計画や債務弁済計画を含めた経営改善計画を策定し、その計画が外部の専門家や有識者で組織された再生審査会で承認された場合に、その求償権を借換えるための保証である求償権消滅保証を行うことができるようになりました。
簡単に言いますと、金融機関との約定弁済(毎月の返済)ができなくなり、保証協会が金融機関に肩代わりで弁済した場合でも、一定の条件のもとで、もとの正常な金融取引の状態に戻してあげようということです。
保証協会は国の制度であり、中小企業の支援を目的としていることから、金融機関より融通の利くことも多く、代位弁済になったからといって、全てを投げ出す必要はないということですね。
さて、一定の条件とは一律決まっているわけではありませんが、下記のような取り組みは最低限必要でしょう。
1 できるだけ可能で誠実な義務(返済や資料提出等)の履行
2 事業の見直しの中で、可能な限りのコストカット
3 不要な資産の売却による負債の縮小
4 黒字体質の構築
事業の見直しについては、過去の売り上げ重視の戦略から利益重視へ、事業の選択と資源の集中投下、一貫性のある成長戦略の構築が求められます。これらを具体的かつ見える化した経営改善計画の策定が必要となるでしょう。
私どもでは、一口に事業再生支援と言っても、小規模零細事業者の場合は、「事業再生支援」と言うより「経営改善への支援」と言ったスタンスで取り組むほうが妥当ではないかと考え、「危機に至った原因が何だったのか」また、「経営改善のためのポイントは何か」などを経営者と一緒に考える取り組みを致しております。
東京で事業再生に関する勉強会に参加
2012年07月10日
一昨日は東京で事業再生に関する勉強会に参加してきました。
リスケ、リストラ、財務分析、私的整理、法的整理、第二会社方式、M&A、担保処分、サービサー、保証協会等の基本と、その実践的使い分け方、見極め方、実例研究を、6時間かけて学ぶ勉強会でしたが、事業再生に携わる場合の心構えから、当初の相談時点の対応方法も含めて、改めて考える内容でした。
事例研究は勉強になります。特に滋賀などでは話題が少ないDDS(デット・デット・スワップ)を使った再生スキームの実例や、最近の金融機関の動きについては最先端の情報を得ることができ大変満足でした。
その一部としては、下記のようなものがありましたので、ご報告します。
保証協会をはじめ競売に持ち込まれるスピードが速くなっていること。
これは、一般の不動産取引が低調であるため優良物件が少ないことや、一般のユーザーの参入が普通になりつつあることなどから、競売物件の人気が高く競売落札の価格が以前より高くなっているためではないでしょうか。
金融円滑化法の終了に向けて、金融機関による債務者の選別が始まっていること。
高利金融や多重債務者は激減していること。
事業再生についても、ネットで主だった情報が簡単に得られることから、専門家といえど、もはや(従来の)専門性だけでは、相談者のニーズを満たせなくなっていること。
B/Sの再生だけでなく、P/Lの再生、V字回復よりもU字回復。対処療法よりも原因療法が見直されていること。
この結果、破産などの単なる法的措置よりも、事業の本質的な再生を援助する専門家のニーズがより高まるということでしょう。
国は、やみくもに中小企業を保護する政策から、新成長分野の企業を中心とした支援政策にシフトしつつあるのではないか?
そのほうが経済効果が上がるという判断です。
リスケ、リストラ、財務分析、私的整理、法的整理、第二会社方式、M&A、担保処分、サービサー、保証協会等の基本と、その実践的使い分け方、見極め方、実例研究を、6時間かけて学ぶ勉強会でしたが、事業再生に携わる場合の心構えから、当初の相談時点の対応方法も含めて、改めて考える内容でした。
事例研究は勉強になります。特に滋賀などでは話題が少ないDDS(デット・デット・スワップ)を使った再生スキームの実例や、最近の金融機関の動きについては最先端の情報を得ることができ大変満足でした。
その一部としては、下記のようなものがありましたので、ご報告します。
保証協会をはじめ競売に持ち込まれるスピードが速くなっていること。
これは、一般の不動産取引が低調であるため優良物件が少ないことや、一般のユーザーの参入が普通になりつつあることなどから、競売物件の人気が高く競売落札の価格が以前より高くなっているためではないでしょうか。
金融円滑化法の終了に向けて、金融機関による債務者の選別が始まっていること。
高利金融や多重債務者は激減していること。
事業再生についても、ネットで主だった情報が簡単に得られることから、専門家といえど、もはや(従来の)専門性だけでは、相談者のニーズを満たせなくなっていること。
B/Sの再生だけでなく、P/Lの再生、V字回復よりもU字回復。対処療法よりも原因療法が見直されていること。
この結果、破産などの単なる法的措置よりも、事業の本質的な再生を援助する専門家のニーズがより高まるということでしょう。
国は、やみくもに中小企業を保護する政策から、新成長分野の企業を中心とした支援政策にシフトしつつあるのではないか?
そのほうが経済効果が上がるという判断です。
破産なんかしないで事業再生 その3
2012年06月13日
当座の資金繰りさえ回ればリ・スケジュールで倒産を回避できます。建設業の場合、基本は受注産業であり、工場等の生産拠点を持つ必要なく事業ができます。今回の事例では材料仕入も下請けオンリーであったので、元請さんに支給してもらうことができました。
大事なことは従業員や外注先の支払いを優先し、協力を最大限取り付けることでした。あとは、税金やリースの支払いでしたが、いずれも低姿勢なお詫びと話し合いとで、遅れながらも支払うことで合意ができました。事務所兼自宅は価値以上の抵当に入っていましたが、これもリスケで乗り切りました。
そして、事業再生とセットでの事業承継の実行です。得意先さんとの話し合いにより、息子さんが起こした新会社へ発注を移していきます。機械関係は時価で新会社へ譲渡します。旧会社は最終的に無資産の状態になりますが、保証人である社長が細々と返済を継続し、破産はしていません。
旧会社は死に体にはなりますが、事業は新会社に見事に承継されそうです。
大事なことは従業員や外注先の支払いを優先し、協力を最大限取り付けることでした。あとは、税金やリースの支払いでしたが、いずれも低姿勢なお詫びと話し合いとで、遅れながらも支払うことで合意ができました。事務所兼自宅は価値以上の抵当に入っていましたが、これもリスケで乗り切りました。
そして、事業再生とセットでの事業承継の実行です。得意先さんとの話し合いにより、息子さんが起こした新会社へ発注を移していきます。機械関係は時価で新会社へ譲渡します。旧会社は最終的に無資産の状態になりますが、保証人である社長が細々と返済を継続し、破産はしていません。
旧会社は死に体にはなりますが、事業は新会社に見事に承継されそうです。