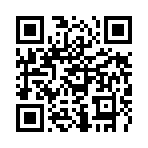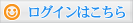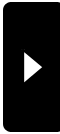生産緑地対策セミナー 生産緑地の2022年問題
2017年08月02日
今日もお目にかかりました間違った生産緑地制度の解説記事。
著名な経済雑誌に、やはり著名な不動産コンサルタント氏の記事です。そして、この方の立場の説明が「第三者性を堅持した」うんぬんです。前も別の方ですが、ありました、「中立な立場で」うんぬんと。
これが枕詞になるほど、不動産コンサルタントの世界では、中立性とか第三者性とかを維持して論説するのは難しいのでしょうね。だから、わざわざ、それを表示しないといけないわけで。でも、本当に中立性とか第三者性とかが維持されているかどうかは、その方の活動を観察し、どういう場で発言されてるかに注目すると、およそ、理解できます。
それはさておき、間違った生産緑地制度の解説では、「期限(だいたいが2022年)を迎えたとき、所有者が病気などで農業に従事できなくなった、あるいは死亡などの場合に、所有者は市区町村の農業委員会に土地の買い取り申し出を行える。」とあります。
これって、もう既に間違いですよね。土地の買い取り申し出に死亡や疾病という理由が必要なくなるのが2022年問題なんですよ!
テレビにも出て専門家として発言される方にして、こういう間違った認識をお持ちなんです。(わざと虚偽発言をされているとしたら、もっと、問題ですが。)間違った認識のもとで解説されても間違った情報を伝えられるだけですから、その他は読むに値しません。
なのに、その記事を見た人が、「これは・・・御一読を。」とか言って、ネット上で薦めています。間違った見解を何もわかっていない人が喧伝する事態です。これでは、間違った対応をする人が居ても仕方がないわけですね。
これではいけないというわけで、微力ながら、正確な情報を伝達するために、次ぎのとおりセミナーを開催します。
このセミナーは、アパート等の建築会社や金融機関とは一切関係がありませんから100%地主さんや賃貸経営者さんの立場に立って本当に役立つお話をします。また、参加者特典として、参加者全員に『農家のみなさん必ず受けよう!相続健康診断」』の小冊子をプレゼントします。
とき 平成29年8月19日土曜日 13時15分~16時00分
場所 京都市北文化会館1階:第2会議室
京都市北区小山北上総町49番地2(キタオオジタウン内)
キタオオジタウンは市営地下鉄北大路駅の真上です。
(地下鉄最寄り1番出入口)
講師 根来行政書士事務所 所長 根来 章
参加対象者 生産緑地所有者及びその後継者などのご親族の方限定
参加費 ¥2,000
(ご同居の親族様2名まで¥2,000で、ご参加いただけます。)
人数 15名限定(お申込み先着順)
個別相談(無料)/ ご希望者にセミナー終了後開催
お問合せ先 根来(ねごろ)行政書士事務所
〒520-3031 滋賀県栗東市綣5-4-21
電話 077-554-3330
このセミナーの主な内容
■2022年になると、何が、どう変わるのか?
■固定資産税・都市計画税は、いつから増加するのか?
■生産緑地制度と相続税の納税猶予との関係は?
■生産緑地の市に対する買い取り申出手続きとは?
■アパートの長期一括借上保証の驚くべき実態とは?
■2022年以降、本当に売り土地が激増するのか?
■アパートを建てると本当に相続税対策になるのか?
■アパート・マンション賃貸経営の本質とは?
■ 2022年に向けて、生産緑地の所有者・承継者・相続人は、今後、どのように対応すれば良いのか?
多くの生産緑地が、その指定から30年を経過する2022年を前に世の中には間違った情報が氾濫しています。間違った情報に振り回されて不必要な対策(特にアパート建築などの相続対策)を選択して、大切な資産を棄損したり失ったりすることのないように、ぜひ、正確な知識を身に着けて頂きたいという趣旨で、このセミナーを開催します。
著名な経済雑誌に、やはり著名な不動産コンサルタント氏の記事です。そして、この方の立場の説明が「第三者性を堅持した」うんぬんです。前も別の方ですが、ありました、「中立な立場で」うんぬんと。
これが枕詞になるほど、不動産コンサルタントの世界では、中立性とか第三者性とかを維持して論説するのは難しいのでしょうね。だから、わざわざ、それを表示しないといけないわけで。でも、本当に中立性とか第三者性とかが維持されているかどうかは、その方の活動を観察し、どういう場で発言されてるかに注目すると、およそ、理解できます。
それはさておき、間違った生産緑地制度の解説では、「期限(だいたいが2022年)を迎えたとき、所有者が病気などで農業に従事できなくなった、あるいは死亡などの場合に、所有者は市区町村の農業委員会に土地の買い取り申し出を行える。」とあります。
これって、もう既に間違いですよね。土地の買い取り申し出に死亡や疾病という理由が必要なくなるのが2022年問題なんですよ!
テレビにも出て専門家として発言される方にして、こういう間違った認識をお持ちなんです。(わざと虚偽発言をされているとしたら、もっと、問題ですが。)間違った認識のもとで解説されても間違った情報を伝えられるだけですから、その他は読むに値しません。
なのに、その記事を見た人が、「これは・・・御一読を。」とか言って、ネット上で薦めています。間違った見解を何もわかっていない人が喧伝する事態です。これでは、間違った対応をする人が居ても仕方がないわけですね。
これではいけないというわけで、微力ながら、正確な情報を伝達するために、次ぎのとおりセミナーを開催します。
このセミナーは、アパート等の建築会社や金融機関とは一切関係がありませんから100%地主さんや賃貸経営者さんの立場に立って本当に役立つお話をします。また、参加者特典として、参加者全員に『農家のみなさん必ず受けよう!相続健康診断」』の小冊子をプレゼントします。
とき 平成29年8月19日土曜日 13時15分~16時00分
場所 京都市北文化会館1階:第2会議室
京都市北区小山北上総町49番地2(キタオオジタウン内)
キタオオジタウンは市営地下鉄北大路駅の真上です。
(地下鉄最寄り1番出入口)
講師 根来行政書士事務所 所長 根来 章
参加対象者 生産緑地所有者及びその後継者などのご親族の方限定
参加費 ¥2,000
(ご同居の親族様2名まで¥2,000で、ご参加いただけます。)
人数 15名限定(お申込み先着順)
個別相談(無料)/ ご希望者にセミナー終了後開催
お問合せ先 根来(ねごろ)行政書士事務所
〒520-3031 滋賀県栗東市綣5-4-21
電話 077-554-3330
このセミナーの主な内容
■2022年になると、何が、どう変わるのか?
■固定資産税・都市計画税は、いつから増加するのか?
■生産緑地制度と相続税の納税猶予との関係は?
■生産緑地の市に対する買い取り申出手続きとは?
■アパートの長期一括借上保証の驚くべき実態とは?
■2022年以降、本当に売り土地が激増するのか?
■アパートを建てると本当に相続税対策になるのか?
■アパート・マンション賃貸経営の本質とは?
■ 2022年に向けて、生産緑地の所有者・承継者・相続人は、今後、どのように対応すれば良いのか?
多くの生産緑地が、その指定から30年を経過する2022年を前に世の中には間違った情報が氾濫しています。間違った情報に振り回されて不必要な対策(特にアパート建築などの相続対策)を選択して、大切な資産を棄損したり失ったりすることのないように、ぜひ、正確な知識を身に着けて頂きたいという趣旨で、このセミナーを開催します。
アパート融資が相続税対策で急増
2017年07月26日
下記は、約3か月前の日経新聞の記事、「アパート融資とは 相続税対策で需要急増、銀行が力 」
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDC22H21_S7A420C1EA2000/
この問題、ずいぶん以前から不動産や相続対策の世界では、警鐘が鳴らされていますが、改めて考えますと、
とりあえず、平成27年1月1日からの「相続税制の改正で課税対象が拡大し、これまで相続税を払う必要がなかった層が新たに含まれることになった」ことに端を発したかのような書き方の記事ですが、実は改正前に相続税を払う必要がなかった層が改正後に負担するようになった相続税はそう大きくありません。
だから、そうした層がアパート建築に走ったということは、ほぼ、ないでしょう。
それよりも、もう少し資産の多い層で資産のうちで土地が占める割合の多い人たちが、そら大変という煽り営業を受けて、アパート建築で相続税対策をやった結果が、賃貸アパートの建築資金をまかなうための融資の急増につながったものと考えます。
でも、その中には、本来、アパート建築をする必要のない人も含まれていると私はみています。
が、しかし、土地が相続税で召しあげられることなく残せて、家賃は保証されているし借入返済は安定的にできて余剰も生まれるとか言われれば飛びつくのも無理ないかもしれません。
でも、この家賃保証が全くの曲者で、記事にあるような「年数が経過すると空室率が上がり、保証額は逆に下がる。」という現実を理解して契約をした人がどれだけいるのでしょうか。
アパートを建てて30年から40年、ずーと採算が合うような好立地ならば、むしろ、サブリースなどする必要はないんですけどね。
それはともかく、相続税の負担軽減ばかりに目が行くと大局的なものの見方が出来なくなるようですね。
それと、相続税の負担軽減の希望とアパート建築の売り上げ増は、変にシンクロする関係にあります。それは、つまり、こうです。
地主さんはたいてい借金してアパートを建てます(現金での建築でも以下の理屈は同じです。)。建物の相続税評価は固定資産税の評価額となりますので時価(請負代金)のざっと6割くらいとなります。それだけでも、相続税負担の面で、お得ですねという話ですが、
実は、建物の場合、実際の請負額が固定資産税の評価に直接、反映することはありません。役所が自分たちの評価基準でほぼ一方的に評価額を決めてくるんです。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o9
すると、とりあえず請負代金が増えれば増えるほど相続税評価とのかい離が大きくなって、相続税負担の面でお得感が増すんです。でも、ちょっと考えれば変ですよね、この話。
このからくりを利用されて、相場より高い建物を買わされているとしたら、素直に喜んでいる場合ではないでしょう。しかも、高い建物を建てるために借りた借金の返済は、もちろん、オーナー持ちですよ。
このからくりについて、言及している人、あんまりないんですよね、なぜか!
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDC22H21_S7A420C1EA2000/
この問題、ずいぶん以前から不動産や相続対策の世界では、警鐘が鳴らされていますが、改めて考えますと、
とりあえず、平成27年1月1日からの「相続税制の改正で課税対象が拡大し、これまで相続税を払う必要がなかった層が新たに含まれることになった」ことに端を発したかのような書き方の記事ですが、実は改正前に相続税を払う必要がなかった層が改正後に負担するようになった相続税はそう大きくありません。
だから、そうした層がアパート建築に走ったということは、ほぼ、ないでしょう。
それよりも、もう少し資産の多い層で資産のうちで土地が占める割合の多い人たちが、そら大変という煽り営業を受けて、アパート建築で相続税対策をやった結果が、賃貸アパートの建築資金をまかなうための融資の急増につながったものと考えます。
でも、その中には、本来、アパート建築をする必要のない人も含まれていると私はみています。
が、しかし、土地が相続税で召しあげられることなく残せて、家賃は保証されているし借入返済は安定的にできて余剰も生まれるとか言われれば飛びつくのも無理ないかもしれません。
でも、この家賃保証が全くの曲者で、記事にあるような「年数が経過すると空室率が上がり、保証額は逆に下がる。」という現実を理解して契約をした人がどれだけいるのでしょうか。
アパートを建てて30年から40年、ずーと採算が合うような好立地ならば、むしろ、サブリースなどする必要はないんですけどね。
それはともかく、相続税の負担軽減ばかりに目が行くと大局的なものの見方が出来なくなるようですね。
それと、相続税の負担軽減の希望とアパート建築の売り上げ増は、変にシンクロする関係にあります。それは、つまり、こうです。
地主さんはたいてい借金してアパートを建てます(現金での建築でも以下の理屈は同じです。)。建物の相続税評価は固定資産税の評価額となりますので時価(請負代金)のざっと6割くらいとなります。それだけでも、相続税負担の面で、お得ですねという話ですが、
実は、建物の場合、実際の請負額が固定資産税の評価に直接、反映することはありません。役所が自分たちの評価基準でほぼ一方的に評価額を決めてくるんです。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o9
すると、とりあえず請負代金が増えれば増えるほど相続税評価とのかい離が大きくなって、相続税負担の面でお得感が増すんです。でも、ちょっと考えれば変ですよね、この話。
このからくりを利用されて、相場より高い建物を買わされているとしたら、素直に喜んでいる場合ではないでしょう。しかも、高い建物を建てるために借りた借金の返済は、もちろん、オーナー持ちですよ。
このからくりについて、言及している人、あんまりないんですよね、なぜか!
土地の2022年問題-虚言なのか無理解なのか?
2017年07月25日
昨日も書きました、土地の2022年問題です。
『また、不動産のプロのなかにも、2022年になったら自動的に固定資産税が宅地並みに課税されるから農家はたいへんなどと間違って理解してる人が多いのに驚かれます。現に、ネット上にはそのようなニュアンスで書かれている論説も多くみられます。』
実際、 「2022年に指定から30年を経過したら、勝手に農地並みの課税から宅地並み課税に移行し、税金の負担が増えることになります。」というような記事が、ネット上にあります。
昨日も書きましたが、「30年経って、自動的に指定が解除されるわけではなく、所有者が解除を望んだ場合にのみ解除されるということ。つまり、望まなければ、固定資産税は農地並みのままです。」
間違った或いは紛らわしい表現を用いて、それからあとは、「お化けが出るぞ!」と恐怖を煽り、それ対策だ、土地に賃貸住宅や商業施設を建てて貸すことだと、誘導(?)していきます。
しかし、これって、どうよと思います。
こういう記事を書いている人の虚言なのでしょうか、単なる無理解なのでしょうか?
『また、不動産のプロのなかにも、2022年になったら自動的に固定資産税が宅地並みに課税されるから農家はたいへんなどと間違って理解してる人が多いのに驚かれます。現に、ネット上にはそのようなニュアンスで書かれている論説も多くみられます。』
実際、 「2022年に指定から30年を経過したら、勝手に農地並みの課税から宅地並み課税に移行し、税金の負担が増えることになります。」というような記事が、ネット上にあります。
昨日も書きましたが、「30年経って、自動的に指定が解除されるわけではなく、所有者が解除を望んだ場合にのみ解除されるということ。つまり、望まなければ、固定資産税は農地並みのままです。」
間違った或いは紛らわしい表現を用いて、それからあとは、「お化けが出るぞ!」と恐怖を煽り、それ対策だ、土地に賃貸住宅や商業施設を建てて貸すことだと、誘導(?)していきます。
しかし、これって、どうよと思います。
こういう記事を書いている人の虚言なのでしょうか、単なる無理解なのでしょうか?
不動産の2022年問題?
2017年07月24日
最近、何かと話題になる不動産の2022年問題について書いてみます。
難しいお話は別として、都市(関東、中部、関西)近郊にある農地のうち、固定資産税の面で低い税率で優遇される代わりに、農地以外に転用(たとえば宅地化)することを、実質、禁じられた農地が生産緑地制度の農地です。
そしてこの禁止が指定から30年の時限政策であるため、2022年にほとんどの生産緑地農地がこの縛りから解放されます。
よって、これを機に大量に宅地化されて市場に供給され、土地価格が暴落するとか言われているのです。
でも、私は一気に宅地化というシナリオは現在の法制度のもとでは現実的でないと考えています。
その理由は、①30年経っても自動的に指定が解除されるわけではなく、所有者が解除を望んだ場合にのみ解除されるということ。つまり、望まなければ、固定資産税は農地並みのままです。
②(これはややこしいのですが、)生産緑地のうち既に相続税の納税猶予制度を受けている場合は、事実上、次の相続が起こるまでは転用しにくいこと。(相続税に相続時にさかのぼって利子税をつけて納税することになるからです。)この割合がおおよそ全体の4~5割というデータもあります。
そして、ある調査(東京に限る)では、相続税納税猶予制度の適用を受けていない生産緑地の今後の利用意向を問う設問に、「指定から30年経過後、すぐ区市へ買取り申出したい」との回答は全体の約8%に過ぎないそうです。そして、最も割合が高いのは「どうするか、わからない」の約53%で、「現在のところ、指定から30年経過後も生産緑地を継続し、農地として利用するつもり」という継続意向が34%を占めているとされています。
東京以外の地域における相続税納税猶予の適用状況や農家の意向は把握できていませんが、こうしてみると、指定から30年経過するすべての生産緑地が、一斉に買取り申出を行うことにはならないと言えそうです。
であるにもかかわらず、一部ではアパート建築などの営業をする業者から2022年問題として煽っての攻勢にさらされている農家もあるようです。
また、不動産のプロのなかにも、2022年になったら自動的に固定資産税が宅地並みに課税されるから農家はたいへんなどと間違って理解してる人が多いのに驚かれます。現に、ネット上にはそのようなニュアンスで書かれている論説も多くみられます。
こうした故意に間違った情報の流布によって誤解が誤解を生み、する必要のない、或いは、してはいけない対策をする農家が続出するのではないかと、私は危惧しています。
難しいお話は別として、都市(関東、中部、関西)近郊にある農地のうち、固定資産税の面で低い税率で優遇される代わりに、農地以外に転用(たとえば宅地化)することを、実質、禁じられた農地が生産緑地制度の農地です。
そしてこの禁止が指定から30年の時限政策であるため、2022年にほとんどの生産緑地農地がこの縛りから解放されます。
よって、これを機に大量に宅地化されて市場に供給され、土地価格が暴落するとか言われているのです。
でも、私は一気に宅地化というシナリオは現在の法制度のもとでは現実的でないと考えています。
その理由は、①30年経っても自動的に指定が解除されるわけではなく、所有者が解除を望んだ場合にのみ解除されるということ。つまり、望まなければ、固定資産税は農地並みのままです。
②(これはややこしいのですが、)生産緑地のうち既に相続税の納税猶予制度を受けている場合は、事実上、次の相続が起こるまでは転用しにくいこと。(相続税に相続時にさかのぼって利子税をつけて納税することになるからです。)この割合がおおよそ全体の4~5割というデータもあります。
そして、ある調査(東京に限る)では、相続税納税猶予制度の適用を受けていない生産緑地の今後の利用意向を問う設問に、「指定から30年経過後、すぐ区市へ買取り申出したい」との回答は全体の約8%に過ぎないそうです。そして、最も割合が高いのは「どうするか、わからない」の約53%で、「現在のところ、指定から30年経過後も生産緑地を継続し、農地として利用するつもり」という継続意向が34%を占めているとされています。
東京以外の地域における相続税納税猶予の適用状況や農家の意向は把握できていませんが、こうしてみると、指定から30年経過するすべての生産緑地が、一斉に買取り申出を行うことにはならないと言えそうです。
であるにもかかわらず、一部ではアパート建築などの営業をする業者から2022年問題として煽っての攻勢にさらされている農家もあるようです。
また、不動産のプロのなかにも、2022年になったら自動的に固定資産税が宅地並みに課税されるから農家はたいへんなどと間違って理解してる人が多いのに驚かれます。現に、ネット上にはそのようなニュアンスで書かれている論説も多くみられます。
こうした故意に間違った情報の流布によって誤解が誤解を生み、する必要のない、或いは、してはいけない対策をする農家が続出するのではないかと、私は危惧しています。
相続における不動産のポジションと専門家
2016年07月23日
先日来、相続に関するとある勉強会に続けて参加しました。
その中で改めて認識したこと・・・それは、相続における不動産のポジションの重要性及びその専門家の実質的な不在という事実です。
私も、いつも言ってますが、日本の相続における遺産の多くは不動産です。
しかも、不動産以外の預貯金、上場株式、生命保険等は、その評価や取扱いについて難しいことは少ないですね。(相続の手続きが煩雑なことについて以外は。)
株式でも非上場株、いわゆる中小企業における非公開株につては、その評価や取扱いについて、難しい面が確かにあります。不動産以外の遺産で、やっかいなのは、これが唯一くらいのものでしょう。
しかも、遺産中でいえば、そのウエートは非常に小さい。つまり、中小企業における非公開株の相続問題は、極めてレアもんなわけです。
ところが不動産は違います。いまや、日本人なら、大なり小なりのマイホームを持っています。マイホームは不動産の相続です。
昭和の30年代以前は不動産持ちがどちらかと言えば少なかったのです。しかし、高度経済成長期を経て、住宅ローンが一般に普及してから、一定の収入があれば誰でもたいていマイホームを持てるようになりました。
そのような状況の中で不動産を買われた人たちの相続が、これから、どっと、起きます。
その不動産の取扱いについては専門性が要求され、一般、素人には非常に扱いにくいものなのです。
しかも、素人だけではありません。一般に相続問題を扱うとされる専門家と思われている資格者でも実は不動産にまつわる特別法や取引実務のことはわかりませんという方が多いのです。
相続税の申告は税理士さん、揉めてしまったら弁護士さんに頼むというくらいのことは、ふつう、誰でもわかるでしょう。
でも、その方々でも、ずばり、実は、不動産が苦手なのです。えっ、何で?
税理士さんや弁護士さんになる試験には、不動産にまつわる特別法や取引実務といった科目はないからです。
それと、弁護士さんに相続問題について依頼するときは、他の相続人と喧嘩すると覚悟してからですよ。
弁護士さんは資格の性格上、相続人全員の代理人にはなれません。なぜ?
相続人同士は、法律用語でいう利益相反関係に立つからです。つまり、相続人全員の間をとりもって円満に解決してもらいたいと考える場合には、弁護士さんは向かないのです。
相続対策もそうですよ。不動産にまつわる特別法や取引実務といった知識がないと正確な評価ができませからね、公平で揉めない遺言書を作るためには、要注意です。
さぁ、あなたは、まず、誰に相談しますか?
相続の相談は、不動産にまつわる法律や取引実務に明るい人にしましょう。そうでないと、かえって、トラブルに巻き込まれたり、後悔することになりかねません。
私の事務所では、不動産相続のコンサルティングを行っています。行政書士と宅地建物取引士の資格を持ち、取引実務に精通していますので、気になる方は一度、ご相談ください!
電話は、077-554-3330です!
その中で改めて認識したこと・・・それは、相続における不動産のポジションの重要性及びその専門家の実質的な不在という事実です。
私も、いつも言ってますが、日本の相続における遺産の多くは不動産です。
しかも、不動産以外の預貯金、上場株式、生命保険等は、その評価や取扱いについて難しいことは少ないですね。(相続の手続きが煩雑なことについて以外は。)
株式でも非上場株、いわゆる中小企業における非公開株につては、その評価や取扱いについて、難しい面が確かにあります。不動産以外の遺産で、やっかいなのは、これが唯一くらいのものでしょう。
しかも、遺産中でいえば、そのウエートは非常に小さい。つまり、中小企業における非公開株の相続問題は、極めてレアもんなわけです。
ところが不動産は違います。いまや、日本人なら、大なり小なりのマイホームを持っています。マイホームは不動産の相続です。
昭和の30年代以前は不動産持ちがどちらかと言えば少なかったのです。しかし、高度経済成長期を経て、住宅ローンが一般に普及してから、一定の収入があれば誰でもたいていマイホームを持てるようになりました。
そのような状況の中で不動産を買われた人たちの相続が、これから、どっと、起きます。
その不動産の取扱いについては専門性が要求され、一般、素人には非常に扱いにくいものなのです。
しかも、素人だけではありません。一般に相続問題を扱うとされる専門家と思われている資格者でも実は不動産にまつわる特別法や取引実務のことはわかりませんという方が多いのです。
相続税の申告は税理士さん、揉めてしまったら弁護士さんに頼むというくらいのことは、ふつう、誰でもわかるでしょう。
でも、その方々でも、ずばり、実は、不動産が苦手なのです。えっ、何で?
税理士さんや弁護士さんになる試験には、不動産にまつわる特別法や取引実務といった科目はないからです。
それと、弁護士さんに相続問題について依頼するときは、他の相続人と喧嘩すると覚悟してからですよ。
弁護士さんは資格の性格上、相続人全員の代理人にはなれません。なぜ?
相続人同士は、法律用語でいう利益相反関係に立つからです。つまり、相続人全員の間をとりもって円満に解決してもらいたいと考える場合には、弁護士さんは向かないのです。
相続対策もそうですよ。不動産にまつわる特別法や取引実務といった知識がないと正確な評価ができませからね、公平で揉めない遺言書を作るためには、要注意です。
さぁ、あなたは、まず、誰に相談しますか?
相続の相談は、不動産にまつわる法律や取引実務に明るい人にしましょう。そうでないと、かえって、トラブルに巻き込まれたり、後悔することになりかねません。
私の事務所では、不動産相続のコンサルティングを行っています。行政書士と宅地建物取引士の資格を持ち、取引実務に精通していますので、気になる方は一度、ご相談ください!
電話は、077-554-3330です!